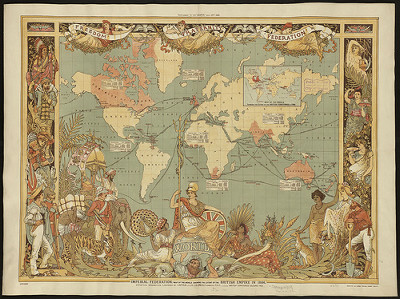「指定通りに文章を書く自動書記人形」「水面の魚を食べる白鳥」など驚異的技巧オートマタの歴史

日本では茶運び人形などのからくり人形が有名ですが、西洋でも「指定した文章を手書きで書き記す人形」など高度な駆動機能を備えた人形「オートマタ」が数多く生み出されてきました。そんなオートマタの歴史について歴史系YouTubeチャンネルのTimelineが解説しています。
Automata: The Extraordinary "Robots" Designed Hundreds Of Years Ago | Mechanical Marvels | Timeline - YouTube

中世ヨーロッパでは街の秩序を保つために「時間」が重視されるようになりました。街中で同一の時間感覚を共有するために大きな時計塔がいくつも建造されました。

時計塔の内部はこんな感じ。大きな振り子やゼンマイ、ヒモなどで時計を駆動させています。

こうした時計塔の生産技術向上に伴って、時計仕掛けを流用したオートマタの開発も活発になりました。

以下の写真はオーストリアのヘルブルン宮殿の庭園に設置されたオートマタです。建物の内部や周囲に貴族や労働者を再現したオートマタが数多く並べられています。

人間が横に並ぶとこんな感じ。非常に大規模な仕掛けであることが分かります。

18世紀に入ると、ゼンマイやネジなどの小型化技術が発展し、小型のボディに駆動部品を詰め込んだオートマタが作られるようになりました。例えば、以下の虫を模したオートマタは羽根を動かしながら前方に進む機能を備えています。

中身はこんな感じ。

以下のオートマタは極小の鳥が羽を高速で羽ばたかせる様子を再現しています。

さらに、「回転運動を上下運動に変換する」といったように運動の方向を変える働きを持つ機構「カム」の開発も進み、オートマタは多様な動きを再現できるようになりました。

カム機構を駆使したオートマタの中でも傑作とされているのが、ピエール・ジャケ・ドローによって作られた「ライター」です。

ライターはペンを持った手を動かして文章を記すことができました。

文章の内容は以下の円盤パーツに「文字を指定するパーツ」をはめ込むことで自由に指定可能。

また、非常に精密な動きを実現しつつ子どもの体程度の大きさのボディ内にすべての機構が詰め込まれているのも大きな特徴です。

以下は発明家のジョン・ジョセフ・マーリンによって作られた銀製の白鳥オートマタです。

銀製の細長い部品を回転させることで、水面(みなも)に似た輝きを再現。

白鳥の首が滑らかに稼働し、魚をくわえます。

以下は、「自動的にチェスをプレイするオートマタ」という触れ込みで大きな人気を得たオートマタ「トルコ人」を再現したものです。トルコ人は人間とチェス勝負を繰り広げることが可能で、ナポレオン・ボナパルトに勝利した記録も残っています。

トルコ人の「非常に複雑な動作を機械化する」というアプローチは当時の技術者に大きな衝撃を与え、エドモンド・カートライトが自動織機を開発した動機にもなったとされています。

ただし、トルコ人の本当の仕組みは「内部に人間が潜んで、腕を操作する」というものだったことが後に判明しています。

・関連記事
映画「ゴースト・イン・ザ・シェル」の芸者型義体の製作舞台裏はこうなっている - GIGAZINE
この世の終わりかと思ったら超大音量の目覚まし時計「スーパーライデン」だった - GIGAZINE
外部動力を必要とせず半永久的に動き続ける高級置き時計「ATMOS(アトモス)」 - GIGAZINE
アナログ時計はなぜ広告で10時10分付近を表示しているのか? - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article History of amazingly skilled automata su….