なぜ賢くて成功を収めた人なのに「愚かなアイデア」に魅了されてしまうのか?

何かの分野で成功を収めた賢い人のはずなのに、明らかに間違った論理を述べていたり、多くの人が疑問に思う過激な思想を語っていたりすることがあります。なぜ成功した人が「愚かなアイデア」に陥ることがあるのかというメカニズムを、ケンブリッジ大学で心理学を研究するロブ・ヘンダーソン氏が解説しています。
Why Dumb Ideas Capture Smart and Successful People
https://www.robkhenderson.com/p/how-dumb-ideas-capture-smart-and
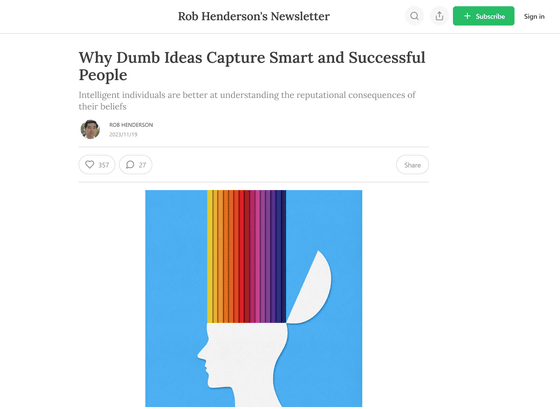
ヘンダーソン氏は、他人を説得する際には2つの方法があるとしています。1つ目は、メッセージを慎重かつ思慮深く検討させ、提示された情報を積極的に評価することでメッセージの内容が真実かどうか見極めてもらう「中央ルート」です。一方で2つ目の「周辺ルート」では、メッセージを受け取る側はメッセージ自体の真偽や利点を考慮することなく、メッセージを発した人の魅力や教育や仕事などのキャリアに基づいて判断します。
周辺ルートは中央ルートよりも、メッセージの受け取り方が受動的な傾向にあります。ヘンダーソン氏によると、人々がますます大量の情報にさらされるようになる中で、中央ルートの積極的な情報への関わり方はできず、周辺ルートがより一般的になっていると言えるそうです。著名な心理学者であるスーザン・フィスク氏とシェリー・テイラー氏は、「人間は、情報処理能力に限界があるため、できる限り近道をする『認知的守銭奴』です」と著書「Social Cognition」の中で書いています。
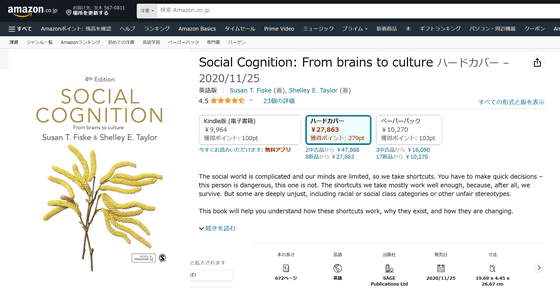
人の情報処理に関する興味深い研究として、ノースウェスタン大学でコミュニケーション学の名誉教授を務めるダニエル・オキーフ氏らが発表した論文をヘンダーソン氏は挙げています。論文では、人々は専門家によるメッセージだと知っているとその内容を信頼しますが、メッセージを読んだ後に「これは専門家によるものだ」と伝えられても、メッセージへの信頼性は高まらないことが示されています。同様に、メッセージを読む前にそれが専門家によるものではないと言われると懐疑的になりますが、メッセージを読んだ後に専門家によるものではないと伝えられても、信頼性は低下しないとのこと。これを受けてヘンダーソン氏は、「情報源が専門家であると事前に知ると、私たちは警戒を緩め、情報能力が低下します」と示唆しています。
説得のメカニズムに加えて、ヘンダーソン氏は著名な心理学者であるレオン・フェスティンガー氏による「他の人が自分と同じ信念を持っているのを見ると、私たち自身もその信念に対する自信が高まる」という、社会的比較プロセスを取り上げています。聴衆は情報の真偽や道徳的是非よりも、自分の信念と合致するかを重視した上で、メッセージを発した人物の周辺情報を探ろうとします。そのため、メッセージを発信する側も、正しいメッセージを発信することよりも、自身の環境や立場を高めることを重視して情報を発信します。
さらに、何を信じるべきかを考えるときに重要視されるのは、私たちから見た周辺情報に限りません。私たちは、メッセージを発する人やその周辺情報を「他人が評価しているかどうか」という周囲の評判を重要視しており、多くの人が何かを信じれば、私たちもそれを信じる可能性は高まるとヘンダーソン氏は示唆しています。また、地位の高い人が信じているものは、私たちも信じてしまう傾向があるそうです。

「人はたとえ真実であっても自分の地位を下げるようなことを言わないようにするものであり、反対にたとえウソであっても自分の地位を高めるようなことを言うようにかりたてられるのです」とヘンダーソン氏は述べています。これは専門知識のないインフルエンサーなどに限らず、科学者の場合でも同様に、真実よりも地位を求めるケースがあります。
ヘンダーソン氏によると、教育を受けていない人々の方が地位や評判に影響されやすいと考える人が多いですが、むしろ地位の高い人やキャリアの優れた人ほど周囲の目を気にするため、中央ルートによる情報自体の精査よりも、周辺ルートの情報で説得される傾向にある可能性があります。一流大学の学生や卒業生は特に、自分自身によるものではない信念や意見、態度に偏った方法で情報や思想を評価し、証拠を作り上げ、仮説を検証する可能性が高くなるとのこと。それに加えて、バークレー大学のキャメロン・アンダーソン氏が主導した研究では、「より高いレベルの教育を受け、より多くのお金を持っている人ほど、『他人の意志決定に影響を与えることが楽しい』『名誉や社会的地位を得たい』という回答に同意する傾向にある」と示されています。
説得のメカニズムや、真実よりも地位を高めようとする傾向、良い教育を受けて地位が高くお金持ちの人ほど偏った考えを持ちやすいといった心理的傾向を総合して、「高学歴や地位の高い人は、仕事や評判を失うことを恐れて、必ずしも信じていないことをメッセージとして表現する可能性が最も高いようです」とヘンダーソン氏は結論付けています。その結論をふまえてヘンダーソン氏は、「賢い人は通常、真実を見つけるのが上手ですが、不条理を生み出すことにも優れています。高学歴で裕福な人が知性と時間を誤って使用すると、不快な結果が生じる可能性があります」と述べています。
・関連記事
多くのインフルエンサーはオンライン講座を運営して収益を得ている、一部のインフルエンサーは詐欺まがいの内容を投稿しているため注意が必要 - GIGAZINE
Twitterはたった10人の「有害なインフルエンサー」で年間25億円も稼ぐとの試算結果 - GIGAZINE
「SNSで流行っている」と感じる物事が「実際には全然流行っていない」現象はなぜ生じるのか? - GIGAZINE
ネット上で他者を攻撃しやすいのは一体どういうタイプの人なのか? - GIGAZINE
「信頼性の低いコンテンツ」を広めるにはわずかな数のTwitterボットで十分であるという研究結果 - GIGAZINE
科学者のツイートの浸透率はあるフォロワー規模を境に指数関数的に増えていく - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by log1e_dh
You can read the machine translated English article Why are smart and successful people so f….












