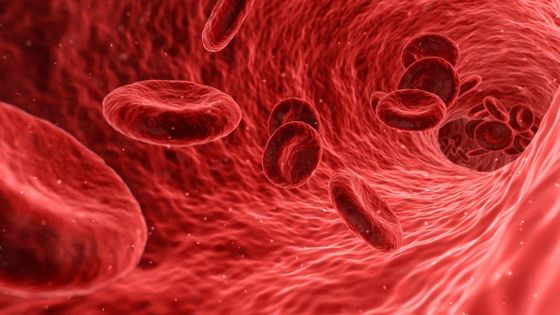「人工子宮」は実現可能なのか?どんな技術的・倫理的課題があるのか?

子宮は受精卵を胚から胎児になるまで育てる重要な器官であり、複数の研究チームは極度の早産で生まれた未熟児(低出生体重児)の生命を維持するため「人工子宮」の開発を進めています。そんな人工子宮の研究の課題や実現できたことについて、生物学系の科学ジャーナリストであるトム・アイルランド氏がまとめています。
To Be Born in a Bag
https://press.asimov.com/articles/artificial-wombs
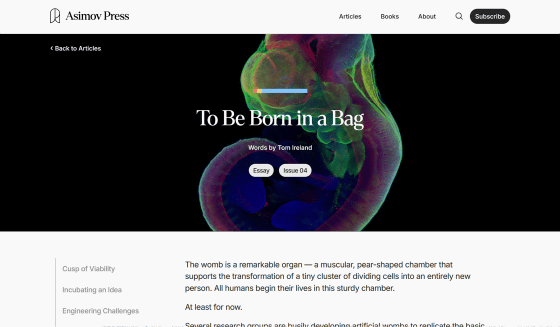
◆未熟児の生存率
妊娠37週未満で生まれた赤ちゃんは早産児とされており、その中でも妊娠28週未満で出生した超早産児のケアは特に難しいといわれています。世界保健機関によると、早産に関する合併症で2019年には90万人が死亡しているとのこと。医療水準が平均を大きく上回っているアメリカでさえ、妊娠24週未満で生まれた新生児の約3分の1が死亡しているほか、新生児が生存できる限界といわれる妊娠22週で生まれた新生児が生き延びられる確率はわずか30%で、そのほとんどが生涯にわたる健康上の問題を抱えています。
これらの超未熟児に対する標準治療は、換気マスクあるいは気管に挿入したチューブを通して肺に酸素を送り込み、ヒートランプで体温を維持し、静脈を通じて水分と栄養を補給するというものです。しかし、あまりに早く生まれた新生児の肺はガスを交換する準備が整っておらず、たとえ特別な低圧人工呼吸器を使ったとしても、未発達の肺組織には修復不可能な損傷が残ることが多いそうです。
人工子宮はこうしたアプローチとは異なり、未熟児を子宮内と同じように液体の中に沈めたまま、血液から二酸化炭素の除去と酸素の供給を行って生命を維持します。デバイスの複雑さはさまざまであるものの、一般に体外式膜型人工肺(ECMO)と呼ばれる人工心肺装置を中心にしています。液体で満ちた人工子宮に未熟児を入れることは、脆弱(ぜいじゃく)な皮膚が外気に触れるのを防ぎ、感染を予防するという点でもメリットがあります。
2017年にはアメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィア小児病院の研究チームが、巨大なジップロックのような人工子宮「Biobag」を用いて、羊の未熟児を4週間育てることに成功したと発表しました。実験に使われた羊の未熟児は母親の子宮内で105~120日育ったもので、これは人間で言うと母親の胎内で22~24週間育てられた胎児に等しいとのこと。
人工子宮「Biobag」で羊の胎児を育てることに成功 - GIGAZINE

また、未熟児を液体で満たされたバッグに入れるのではなく、従来の新生児保育器に入れたまま小型のECMOに接続し、肺だけを特別な成長刺激液で満たすというアプローチも検討されています。このアプローチは既存のシステムとそれほど大きな変更がないため、医療機関にとって採用しやすい可能性があるとアイルランド氏は述べています。
◆人工子宮の歴史
人工子宮という言葉には未来的なイメージがありますが、人工子宮を作ろうという取り組み自体は1950年代にさかのぼります。1953年に、心臓手術中の患者に酸素を送り込むために最初の人工心肺装置が使用されたことで、研究者たちは「体外循環」を活用できる他のシーンの研究を開始しました。そこから「自力で呼吸できない未熟児の生命を維持する」というアイデアにたどり着くのは必然であり、1954年には羊水で満たされたタンク、合成へその尾、血液ポンプ、人工腎臓、給湯器が含まれる人工子宮の特許も出願されました。
1954年にはスウェーデンの研究チームが、中絶した妊婦から得られた「生存可能な人間の胎児」を用いて、静脈から採取した血液を酸素化して体内に戻す単純な回路に接続するという人工子宮に関する初期の人体実験が行われました。胎児は羊水を模倣したアイソトニック(等張)なグルコース溶液に沈め、5~12時間生存させることができたと報告されています。現代の観点からするとこの人体実験には倫理的な課題がありますが、同様のデバイスの研究は1960年代にも続けられ、1969年には羊の未熟児を50時間以上生存させることができるようになりました。
また、マンモスの復活を目指すバイオテクノロジー企業・Colossal Biosciences(Colossal)は、マンモスのDNAとアジアゾウの幹細胞を組み合わせて作り出したハイブリッド胚を、最初から最後まで人工子宮を用いた体外発生プロセスで生み出すことを計画しています。記事作成時点で、胚の段階から胎児になるまで成長した前例はなく、Colossalの目標はかなり野心的なものといえます。

◆人工子宮の技術的課題
すでに動物実験で一定の成果を上げている人工子宮ですが、これを人間の未熟児に適用する上ではさまざまな課題があります。その中で最も大きいとアイルランド氏が指摘しているのが「人工子宮の小型化」です。これまで人工子宮の実験に使われてきた妊娠105~120日頃の羊の未熟児は、発達レベルでいえば人間の妊娠22~23週の胎児と同等であるものの、その体重は3.5kgと一般的な新生児と大差ありません。これに対し、人間の未熟児の体重は0.5kg程度であることも多いため、人工子宮の大きさも羊の未熟児で使われたものより小型化しなくてはならないとのこと。
人工子宮を小型化するには、血管に挿入するカニューレをはるかに小さいものにする必要があるほか、体外システムと未熟児の体内を循環する血液の圧力も繊細に調整する必要があります。また、妊娠20週台の赤ちゃんは急速に成長してわずか数週間で体のサイズが2倍になることもあるため、人工子宮はこれにも適応できなくてはなりません。ミシガン大学で人工子宮を研究しているジョージ・ミカリスカ教授は、「多くの人は『小型化なんて大した課題じゃない』と言うでしょう。確かにそれは可能ですし、私たちは前進していますが、簡単なことではありません」と述べました。
人工子宮に未熟児を接続することで起きる課題には、「血液が異物と接触すると凝固してしまう」という点も上げられます。一般の患者にECMOなどの生命維持システムを使用する場合、ヘパリンなどの抗凝固薬を投与して血液をさらさらにしますが、これを未熟児に使用すると未発達な脳内血管で出血のリスクが高まるとのこと。有望な解決策としては、血液が通過する時に天然の抗凝固剤である一酸化窒素を放出するポリマーコーティングを用いる方法があり、羊を使った2023年の研究でもその有効性が確認されています。
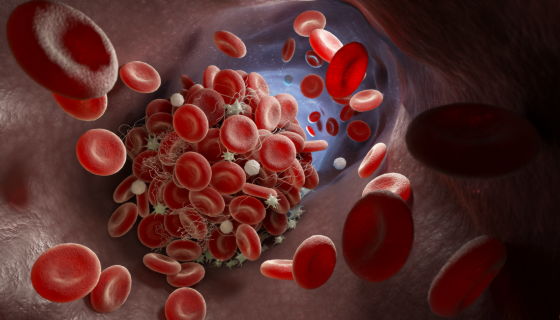
そして、未熟児として生まれた赤ちゃんを人工子宮に移すことそのものにも課題があります。赤ちゃんは生まれて初めて息を吸うことで体に生理学的な変化が起こりますが、人工子宮で生命を維持するにはこの現象を避けると共に、体温の変化、空気への接触、光や大きな音といった要因も考慮しなくてはなりません。動物実験では全身麻酔を施した母親を帝王切開し、オピオイド鎮痛剤を注射した胎児をへその尾が付いたままECMOに接続し、正常な血流が確保されてからへその尾を切断します。しかし、この方法は非常に複雑であり、緊急時や予期せぬ早産で実行できるものではないとのこと。
オランダ・アイントホーフェン工科大学の研究チームは、赤ちゃんを産道から直接液体で満たされたバッグに移す技術や、帝王切開で取り出された赤ちゃんを直接人工子宮に引き込む技術のモデル化を開始しています。理論的には、この手順が確立すればさらに多様な早産シナリオで人工子宮が使えるようになりますが、この場合は装置と血管の接続を液体の中で行わなくてはならず、ただでさえ難しい手術がさらに困難になるとみられます。
アイルランド氏は、「どちらのモデルが最適に機能するのかはさておき、この分野で働く医療従事者にとって、赤ちゃんを密閉された液体で満たされたシステムに移すことはまったく新しいパラダイムであり、母体と赤ちゃんの両方にリスクを追加する可能性があるという事実はありません」と指摘しました。
これらの他にも、発育中の胎児が子宮内で母親から受け取っている複雑な免疫機構やホルモンの理解が進んでおらず、これを人工子宮で再現するのは難しいという問題もあります。一部の研究者らは、自分たちが開発するデバイスが複雑な子宮の化学的環境を再現しておらず、機械的な生命維持装置でしかないことを認め、人工子宮ではなく「人工胎盤」という言葉を使っているそうです。

◆人工子宮の倫理的課題
フィラデルフィア小児病院の研究チームが開発した人工子宮「Biobag」の動物実験の有望な結果を受けて、アメリカ食品医薬品局(FDA)は2023年からヒト臨床試験の可能性について検討を始めています。しかし、未熟児を対象に人工子宮を実験することは、想像しうるほとんどの臨床試験よりも高リスクなものになる可能性があります。
妊娠24週を超えて生まれた未熟児は、従来のケアであっても生存する可能性が高いため、効果が未知数な人工子宮の臨床試験をテストすることは非倫理的に思われます。一方で、さらに早く生まれた未熟児は感染症や炎症などの合併症に苦しんでいる可能性が高く、ECMOに接続しても生き延びられる確率は高くないとのこと。
問題を複雑にしているのが、「アメリカ国内だけで見ても未熟児の転帰が大きく異なる」という点です。一部の大病院では、妊娠22週目の未熟児の生存率がアメリカ平均の2倍以上に達しており、時には妊娠21週目の未熟児を生かすこともあるそうで、同じ段階の未熟児でも病院によって生存率は大きく変わってきます。これにより、医師が人工子宮を試すための一般的なガイドライン作成を難しくしています。
さらに、Colossalが開発している完全人工子宮が実現すれば、子宮に影響が及ぶ病気や障害によって代理出産以外の方法で子どもを持つことができない人に、「完全な体外発生プロセスで子どもを産む」という新たな選択肢が開かれることになります。これは希望でもありますが、「医師が事実上の『生命の創造者』になってしまうのではないか」「子どもが体外発生プロセスで生まれたことを知るとどのような影響があるのか」「女性が生殖における生物学的役割から解放されることがどのような影響を及ぼすのか」「体外発生プロセスを悪用して兵士や奴隷を大量生産するリスクにどう対処するのか」など、さまざまな倫理的課題も提起します。

アイルランド氏は、記事作成時点では一般的になった体外受精もかつてはSF作品に出てくる突飛なアイデアとされており、さまざまな懸念があったものの、今では数百万人の人々に恩恵をもたらしていると指摘。「将来的には人工子宮技術もそうなるかもしれません。人工子宮技術を阻む技術的な課題は依然として大きいものですが、その多くは数年以内に解決されそうです」「母親の子宮の外で妊娠・出産する赤ちゃんは、私たちが考えるより早くやってくるかもしれません」と、アイルランド氏は述べました。
・関連記事
人工子宮「Biobag」で羊の胎児を育てることに成功 - GIGAZINE
3Dプリンターを使って人工の胎盤を作成することに成功 - GIGAZINE
人工的に作られた子宮でウサギを自然妊娠させることに成功 - GIGAZINE
培養幹細胞から「発生2週間後のヒト胚のほぼ完全なモデル」を作成することに成功、謎の多い発生初期の研究に役立つ可能性 - GIGAZINE
人の顔は子宮内の圧力によって形作られる可能性があるという研究結果 - GIGAZINE
致命的な遺伝性疾患を「母親の子宮の中」にいる時から治療し始めることに成功 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Is an 'artificial womb' possible? What t….