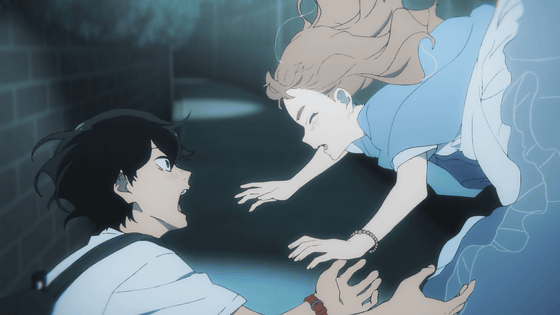「映画 えんとつ町のプペル」を制作したSTUDIO4℃の田中栄子プロデューサーにインタビュー

2020年12月25日公開の「映画 えんとつ町のプペル」など、STUDIO4℃を率いて多数の作品を世に送り出してきた田中栄子プロデューサーにインタビューを実施しました。本作は監督・廣田裕介さん、アニメーション監督・佐野雄太さんなど、STUDIO4℃の生え抜きが中心となり形にした作品。いったい、スタジオを率いるプロデューサーはどのようにして作品を形にしていったのか、そして、そもそも田中さんはなぜプロデューサー業に就いたのか、など、さまざまな質問をぶつけてみました。
『映画 えんとつ町のプペル』公式サイト | 大ヒット上映中!
https://poupelle.com/
GIGAZINE(以下、G):
基本的なことからお聞きするんですけれど、STUDIO4℃の公式サイトに「STUDIO4℃はこうしてできた」というページがあって、「STUDIO4℃の名前は常に新鮮でいるために鮮度を保つ最適温度である4℃からとったらしい(冷蔵庫内の温度は4℃)」と書いてあるんですけれども……
田中栄子プロデューサー(以下、田中):
それは少し違いますね(笑)。水の密度が一番高いのが4℃という、「high density」の意図です。密度の高い仕事をしますという意味と、温度の変化に対して拡散しますという意味で使っております。何かのインタビューの時に「それって冷蔵庫の温度ですよね?」と言われて「そうです、物質が一番安定してるんです」という風な言い方をした覚えがあって、そちらが面白かったので使ったんだと思います。
G:
なるほど。
田中:
その時に「物質が一番安定している状態ということは腐らないということであり、『自身の作っている作品は生涯腐りません!』というメッセージも込めました」と言ったんですけれど、冷蔵庫の話の方が面白かったんですね(笑)
G:
以前、ブログサービスのJUGEMに『鉄コン筋クリート』のテンプレートが提供されたことがあります。その際にインタビューが行われていて、田中プロデューサーは「どういう仕事をしているんですか?」と問われて「特に制作のプロデューサーとしては、スタッフィング、キャスティング、シナリオの編纂、どういう世界観にするか、どういう色彩設定にするかという作品イメージの決定に携わっています。製作チーム全体を、同じ着地点に向かわせるということですね」と回答されていました。『映画 えんとつ町のプペル』の場合は、プロデューサーとしてどのように携わっていくことになったんですか?
田中:
答えた内容がもうちょっと激しくなったって感じでしょうか……。もうちょっと、作品に根幹的に関わっていますね。
G:
「根幹的」ですか。
田中:
私がプロデューサーをしている会社は2つあって、「Beyond C.」という会社と「STUDIO4℃」という会社です。「Beyond C.」では製作・企画を主に行い、作品のファンディングや製作管理をしています。「STUDIO4℃」ではシナリオから作品完成までの大きな道筋をつけるということ。一番最初のシナリオで世界観を構築し、人物像というものをクリアにし、設定として起こし、しっかりとこの作品がどっちを向いて、何をどういう風に作っていくのかという方針出しを行っています。チームがかなり多岐に渡りますので、一人一人が同じ方向を向けるように指標を指し示すというか、ブレないように常に見守っていったり、打ち合わせをしたりするということです。

田中:
今回の『映画 えんとつ町のプペル』に関して言うと、監督の廣田はSTUDIO4℃の生え抜きなんですよ。大学を卒業して、ちょっとバイトをした時期が数か月あったようですが、そこからすぐSTUDIO4℃に来て、最初から演出という仕事をして、本作が映画監督デビュー作になります。それ以外のメインスタッフ達もほとんど全部STUDIO4℃の生え抜きなんですね。『映画 えんとつ町のプペル』はそういう意味でSTUDIO4℃の全員が一丸となって取り組んだ作品であり、むしろそうしないとできなかったという、STUDIO4℃初めての長編3D映画作品なんですよね。
G:
生え抜きということは、コミュニケーションもかなりとりやすかったんですか?
田中:
そうですね。ほとんどみんなSTUDIO4℃しか知らない人たちですからね(笑) すごいチームだと思います。
G:
チームを見守る立場だという田中プロデューサーは、AnimeJapan 2016の「アニメ創りの世界へようこそ!」というクリエイションセミナーで、自身のキャリアなどについて話をしておられます。セミナーの様子を伝えるAbemaタイムスの記事によると「学生の頃からアニメ一筋だったのかと思いきや、大学時代は日本語教授法を専攻していたという田中氏。卒業後は海外で日本語教師になるつもりが、バイク事故であえなく断念」とあります。
田中:
(笑)
G:
さらに「広告代理店に就職するも、上司がアニメ業界に転職し、その流れで自身も日本アニメーションに入社。気づけばアニメの世界にどっぷりつかっていた、という意外な経歴が明かされた」と続きます。記事で指摘されているようにアニメ一筋というわけではないキャリアなのですが、「日本語教授法」を専攻していたのはなぜだったのですか?
田中:
私は青山学院大学の英米文学科で英文学を学びつつ、日本をいつ脱出しようかと思っていたんです(笑)。それで大学を卒業してから国際部に入りまして、国際部の「日本語教授法」という授業を受けて「そこそこ英語ができれば、海外へ行って日本語は得意だから、日本語の先生になるぞ」と思っていました。ところが、バイク事故に、という。
G:
おお、なるほど。それで、日本アニメーションに入り、制作部でプロデューサーとデスクと制作進行の3役を一人でこなした、というすごいキャリアへつながっていくんですね。
田中:
最終的にそういうことです。言えないような出来事もいろいろとあって、ということですね(笑)
G:
(笑) 2006年に行われたインタビューでは「私は基本的に、自分はものすごく普通の人だと思ってますから。作品に入り込み過ぎず、普通の人が観ても分かるという事を、プロデューサーの視点から見ていく。そういう事が求められているという自覚で作品作りをしていました」という話が出ています。これは「自分がものすごく普通の人だ」と自覚する何かがあったのですか?
田中:
ふふふ、そうですね。大体、邦画でも洋画でも、私の見た映画は大体流行っているという点です。「私はすごいポピュラリティが高いんだ」と思いました。
G:
なるほど、多数派であるという意味で「普通の人」と。
田中:
そうです。絵画を鑑賞しても「人と違った角度や違った目線で新しい発見をする」というよりは、普通に感動を覚えます。非常にポピュラリティが高い見方をするという風に自己評価しています。

G:
絵画といえば、ちょっと話はずれますが『Genius Party』のときのインタビューで絵画のたとえが出ていました。「絵画って、やっぱり作者の人となりも見たいじゃない。それを知る事によって、例えばその画家が耳を削ぎ落としてまで求めたものの凄さみたいなものが、さらにグッと伝わってくるでしょう。そういうドラマが『Genius Party』にもある。作品自体を切り離されたメッセージとして受け取るんじゃなくて、作り手の思いが受け手の中にもシンクロして、作品が50%、そして作り手と受け手の気持ちが50%、合わせて200%みたいなね。計算合わないけど(笑)受け手の受け入れる力こそが、作品を凄くしていくと思ってるから。」という話でした。本作では、作り手と受け手の気持ちはどうなりそうでしょうか。
田中:
『Genius Party』はひとりひとりのいわゆる天才たち、クリエイターたちが、「自分のもともと持っているものを吐き出してやろう」という意気込みで作っていて、彼らの個性や表現力といったものの影響が受け手に現れてくるんじゃないかなと思って言った言葉だったと思います。
そういった『Genius Party』という作品と、もともとエンターテインメントを目指している『映画 えんとつ町のプペル』は違いがありますね。『映画 えんとつ町のプペル』の場合、作品というもの自体がいわゆる「総合著作物」であって、たとえば「監督」だけでも監督のほかに美術監督、作画監督、CGI監督、撮影監督、音響監督と監督だらけです。それぞれの監督たちが掛け算で能力を高め合って作るというエンターテインメント作品なので、そういった点からどれだけ作品力が高いかというのを評価してもらえればと思っています。
G:
総合著作物で多数の「監督」が携わっているという点には「スタッフが生え抜き」というのが関係しますか?
田中:
そうですね、『映画 えんとつ町のプペル』は本当に「アニメーションというのは総合著作物である」と言える作品だと思います。ひとりひとりがそれぞれの監督業の分野のなかで独立して自分たちの能力を発揮するというスタンスを完全に守り抜きました。逆に侵害しているところがあったら、「そこはもう他に任せたんだからそのまま託そうよ」と判断するようなチームの方針でした。仮にそこが弱かったらテコは入れますし、そこが未熟だったらサポートを入れますけれど、それぞれがたとえ初めてであろうと、責任を持ってやるという風に方針を決めると、スタッフひとりひとりも成長するんですよね。人が何を作れるか、その人たちがどう力を伸ばせ、表現できるかということを、どんな作品をつくるときも目指していると思います。

G:
田中プロデューサーは「私なんか誉められると木に登っちゃうタイプで(笑)、『田中さん偉いね』なんて言われて頑張ったりしてるわけです。実際、実はけなす事って簡単だし、けなして自分が偉くなったような気になったとしても、それで自分はちっとも輝かない」という話をしておられたことがあります。改めてプロデューサーの視点から見て、スタッフのここは褒めるべきだったと感じる点はありますか?
田中:
たくさんありますよ。まずスタッフがいなければこの作品は完成してませんしね(笑)。それにクオリティに対するあくなき追求心。決して諦めたり、投げ出さない根性。もちろん素晴らしい感性と表現力、才能。ただ、その前に失敗もたくさんしているんですよ。
G:
失敗?
田中:
そうです。作品を作り始めた段階からとにかくたくさん……。たとえば、背景さんがいないまま作っちゃったとか。美術設定自体はどんどん起こしていたんですけれど、美術設定がどんどん複雑で大量になればなるほど、それを美術ボードにし、背景にしていくというところに目も手も回っていなかった。美術ボードを作り始めたのは2019年10月ごろの話で、1年でボードを作り背景までこぎ着けました。
G:
おお……。そもそも、『映画 えんとつ町のプペル』の作業はいつ頃から取りかかったのですか?
田中:
シナリオメイキングが2017年冬くらいからスタートして、西野さんと打ち合わせを重ねました。最後は2018年夏に西野さんが八ヶ岳にこもって、決定稿が8月中旬あたりに上がってきました。それが、第12稿でした。
G:
12稿……!?
田中:
はい。ゴリッゴリ書き直すんですよ、西野さん。すごいです。素晴らしいなと思うのは、私たちがアイデアを出すと「あ、それいいですね!」って、すぐに書き換えてくるところです。ダンスシーン、トロッコシーンの追加や、ローラのセリフ「絶対に帰ってくるんだよ!」の追加、どんどん良くなるから、面白いです。

G:
筆が早いんですね。
田中:
はやい!それで、すぐ打ち合わせ。どんどん変更しては打ち合わせをして、どんどんどんどんコンテが修正されて描かれていくわけです。2018年夏からコンテ作業に入りましたが、そこからも何回か西野さんからシナリオの変更がありました。コンテ作業は当初は3人ぐらいで、西野さんの「そのまんま」をできるだけコンテに生かそうという方針でやっていました。完成までの半年間で、監督は「バイブル」という、世界観や、キャラ設定として「こいつは本当はアイスクリームが好き」とか、驚くほど細かい設定を作っていましたが、「これをみんなにわからせるのは無理だから、いったんしまおう」と。
G:
すごい(笑)
田中:
コンテは2019年3月に1回上がりましたが、たぶん2500カット、2時間半ぐらいあったので、それを一回り小さくしました。その段階で西野さんが西野さんのファンを集めて素人によるアフレコみたいなことをやったんです。ところが、その仮アフレコ素材を使って作打ちを始めてしまって「ちょっと待った!」ということもあって(笑)
G:
それは大変な……。
カット袋の山。『映画 えんとつ町のプペル』制作では紫色のカット袋が使われていました。

田中:
とにかく映画の尺にしなくちゃいけないということで、まず1回、Vコンテに上げて、カッティングをして、私とアニメプロデューサーの長谷川舜と監督の3人で修正セリフを入れてできあがったのが2019年9月です。ところが通してみると、そこそこ破綻もあるし構成も分かり難い所も多く、再編集。欠番を出し、追加シーンを足して、セリフも変更して、かなり作業も進んでいたので、スタッフからものすごいブーイングを受けながら、2019年12月に修正コンテがついに完成、ガイドの声を声優さんのものに入れ直しました。
G:
良かった。
田中:
かなり変えてしまったので、ドキドキして西野さんに渡したら、西野さんはそれに合わせて、また全部シナリオを書き換えてくれました。これが「シナリオ最終稿」ですね。普通はなかなかそうは行かない。けれど、西野さんは良いと思ったら、前向きにどんどん受け入れてくれるので、本当に素晴らしいと思いますよ。また、アニメーションに関してはプロであるSTUDIO4℃に絶対的に任せてくれる。ダメ出しは一切なかったですね。
G:
そういう経緯があったんですね。
田中:
だから、第1稿といったん完成した第12稿、最終稿は構成もセリフもシーンも、かなり違います。まだまだやらなければいけない事はいっぱいあったとは思いますが、この製作スケジュールの中ではかなり頑張ったと思いますよ。
G:
そこまで作り替えるというのは、これまでの作品でもわりとあることなのですか?
田中:
いえいえ。
G:
これは整理だけでも大変そうな……。
田中:
大変ですね、今回は大変な事がたくさんありましたね。Vコンを更新してバージョンアップする方法を指示してたんですが、監督は反対で、プロデューサーの長谷川と一緒に、一方で別の作り方で作業していました。それを見つけたんです(笑)。が、長谷川からも「田中さんのやり方は、意味がないと思います」と言われて、作業は3カ月で中止しました。キャラクターのモデルも、監督がかなり精密なところまでこだわったので、なかなか完成しなかったんですよ。それでキャラクター監督の今中さんにすべての権限を渡すように切り替えて。
G:
「とにかく完成させないと」という方向へ。
田中:
そうです。彼女はものすごく造形力の高いクリエイターなので「監督がどこにこだわるのかはわかっているから任せてください」と。
G:
なるほど……作業をしていて「うまくいかない」に対応するような感じでしょうか。
田中:
トライアンドエラーでしたね。3Dアニメーションなので「絵本が動く」ということをよく考えています。ところが、テクスチャを素晴らしい状態で開発したためにレンダリングが重たくてマシンが動かなくなるという大失敗もありました。レンダリング時間を確認したら1カット「200時間」とかね。
G:
次から次へと混乱が出てきますね。
田中:
モデルにもしっかり線や影やハイライトをつけて、1つのキャラクターだけで6レイヤーもあるんですよ。最後の方の戦闘シーンなんて300人もいて、1人ずつ6レイヤー持っているわけですよ。もうね、カット52は1000レイヤーはいきましたね。キャラクターは3人しかいないのに。
G:
それはマシンが止まりそう(笑)
田中:
ハプニングの連続でした。6月末で、やっと14カット完成して、9月末で70カットしか完成してないのです。どうやって初号1465カットの完成を迎える事ができたのか、全く奇跡です。こうして話をしていると面白いことみたいに聞こえちゃってますが、本当に大変でした。しかもコロナ禍でしたからね。

G:
本当ですね……。
田中:
前半の質問の所に戻ると、「プロデューサーとして何をしたか」の「根幹的」というのは、世界観開発、構成、シナリオ、そして、現場のフローチャートの構築と、各セクションがやる役割と専門性を加味して、それぞれ独立して責任を持って作業してもらいクオリティを担保するようにチーム作りをした。もちろん音楽も含め音響制作においても、この作品を完成させた!というところだったと思います。
G:
すごいところを乗り切った感じですね。いやー、作品の以外のことまでいろいろありがとうございました。
「映画 えんとつ町のプペル」は大ヒット上映中です。
『映画 えんとつ町のプペル』 特別動画:プペル編 - YouTube

『映画 えんとつ町のプペル』 特別動画:ルビッチ編 - YouTube

『映画 えんとつ町のプペル』 特別動画:スコップ編 - YouTube

・関連記事
アニメ制作会社ボンズ・南雅彦代表インタビュー、「ジョゼと虎と魚たち」をアニメ化する意味や生み出した作品への思いを語ってもらった - GIGAZINE
「楽しいアニメーション制作」を描き出す「映像研には手を出すな!」プロデューサーのチェ・ウニョンさんにインタビュー - GIGAZINE
「映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」京極尚彦監督&近藤慶一プロデューサーインタビュー、「子どもが『誇らしい』と思える展開を」 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, アニメ, 映画, インタビュー, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Interview with Eiko Tanaka, producer of ….