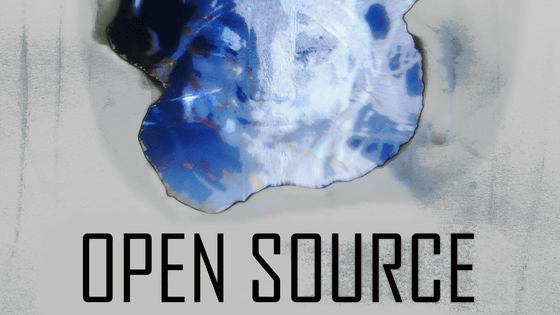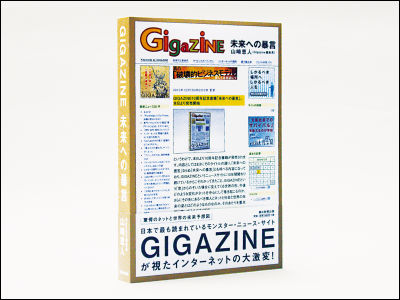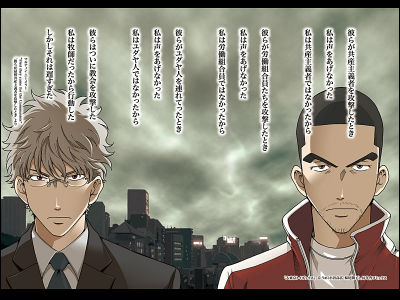デザイン案公募中の「同人マーク(仮)」の基本的な考え方や使い方などまとめ
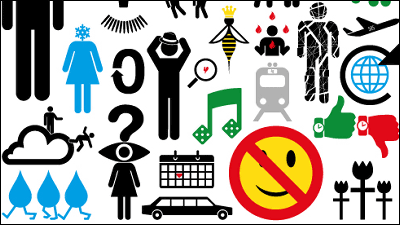
by Viktor Hertz
同人活動に関する著作権の意思表示ツールとして「同人マーク(仮)」のデザイン案が2013年7月17日(水)から7月28日(日)24時までの間、公募されることになりました。既に2013年晩夏に予定されている講談社「少年マガジン」における赤松健氏による新連載のマンガからこの公募で採用された「同人マーク(仮)」が順次採用される予定となっています。
「同人マーク(仮)」のデザイン案の募集のお知らせ | commonsphere
http://commonsphere.jp/archives/286
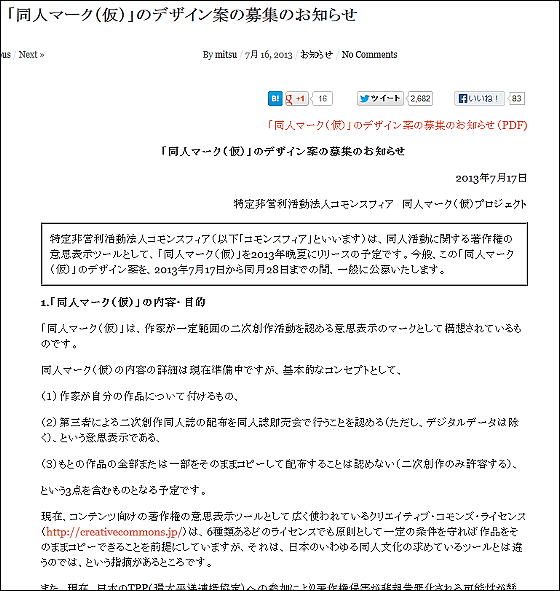
選考委員は以下の5人となっており、「週刊少年マガジン編集長」が入っているのがポイント。つまり、本気で現在連載中のマンガなどに適用していくつもり満々、ということです。
・赤松健(漫画家、Jコミ代表)
・菅原喜一郎(講談社週刊少年マガジン編集長)
・ドミニク・チェン(コモンスフィア理事)
・中山信弘(明治大学特任教授、東京大学名誉教授、コモンスフィア理事長)
・福井健策(弁護士、日本大学芸術学部客員教授)
実際に選考委員の一人であり、自分のマンガで使う予定となっている赤松健氏は自身のTwitterで以下のように発言しており、「講談社公認」というのがポイント。
「同人マーク(仮)」のデザイン案の募集のお知らせ http://t.co/Vcqu326FEr ★2次創作同人誌を、即売会の時だけ認める「同人マーク(仮)」のプロジェクトがスタートしました。コモンスフィア(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)主催で、何と講談社公認です。
— 赤松健 (@KenAkamatsu) July 17, 2013
以下のツイートによると、TPPによる著作権の非親告罪化、つまり著作権を持っていない人間による密告、あるいは妬み・嫉み・恨みによる通報などで同人・二次創作界隈がめちゃくちゃになることを先回りして対抗して防止する狙いもあるようです。
「同人マーク(仮)」のデザイン案の募集のお知らせ http://t.co/Vcqu326FEr ★この実証実験が成功すれば、2次創作同人誌がとても安全に頒布できるようになるでしょう。またTPPで著作権侵害が非親告罪化されても大丈夫です。デザインの選考委員も豪華!
— 赤松健 (@KenAkamatsu) July 17, 2013
マークの基本的コンセプトは以下3点のようになっており、これらが基本的な考えとなります。
◆1:作家が自分の作品について付ける
◆2:第三者による二次創作同人誌の配布を同人誌即売会で行うことを認める(ただし、デジタルデータは除く)という意思表示
◆3:もとの作品の全部または一部をそのままコピーして配布することは認めない(二次創作のみ許容する)
「2」の第三者とは一体誰のことか?という点については以下のように解説されており、「第三者=同人作家」という解釈でOKです。
@mami_tuchino 第三者は同人作家のことです。完全デジタルは除外ですが、マークの追加文字で公認することは可能です。
— 赤松健 (@KenAkamatsu) July 18, 2013
また、「2」によると「同人誌即売会で行うことを認める」、つまり同人誌即売会当日以外は認めない(要するにワンフェスの一日だけの当日版権システムと同じ)ということなので、ショップ委託やデジタルデータによるDL販売はどうなるのか?という点については「追加文字で公認」ということで、自分でOKすれば問題なくできるようになる、という感じになっています。このことは以下のツイートでも示されています。
@hikottan 作者がDL販売まで公認したい場合は、追加文字で公認できます。もしTPPが入ったら、マークが無い二次創作DL販売は全滅する危険性がありますね。
— 赤松健 (@KenAkamatsu) July 17, 2013
@Josui_Do 同人ショップへの委託を、作者がマーク(+追加文字)で認めていない場合は、今まで通りグレーとなります。
— 赤松健 (@KenAkamatsu) July 18, 2013
これらはいわゆるCCライセンスが適用されているものであっても「ただし作者が認めた場合はこの限りではない」という意味の部分と基本的な考え同じであり、基盤部分は上記3点を使って気軽に利用してもらい、それ以外の細かい部分での個別許諾はもちろんOKで自由にしてかまわない、という解釈になっている、というわけ。
何より、単にマークを提案するだけでなく、それを自身のマンガ作品に適用するという実行力の部分があるため、このマークが普及すれば、現在の著作権制度の最大の問題点である「著作権を持っている創作者本人よりも、創作をしていない側の人間や企業が一番儲かっている」という事態を是正し、ごく一部の人間だけでなく、広くさまざまな人間が創作物で利益を得て文化を発展させていくという著作権の本来あるべき姿を目指すことも可能になりそうです。
・関連記事
「同人誌ができるまで」のムービーを印刷所が公開、製本の様子などが紹介される - GIGAZINE
センスではなく具体的に解説する「同人誌やイラストの美しいデザイン100」 - GIGAZINE
イラストを狙った通りの印象に仕上げるポイントを300枚以上の作例を使い解説した「同人誌やイラストを短時間で美しく彩る配色アイデア100」 - GIGAZINE
チャリティーイベントでサンタの代わりに著作権団体がやって来た - GIGAZINE
「ハッピーバースデートゥーユー」がアメリカの映画やテレビドラマであまり歌われていない理由 - GIGAZINE
ファイルコピーを神聖な行為だとする「コピー教」がスウェーデン公認宗教に - GIGAZINE
Megaupload閉鎖後に映画の興収が減少、海賊版の宣伝効果は規模に反比例 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, デザイン, Posted by darkhorse
You can read the machine translated English article Summary of basic idea and usage of "Douj….