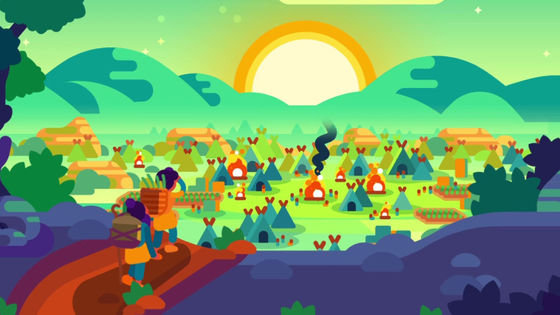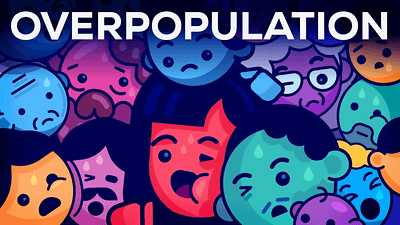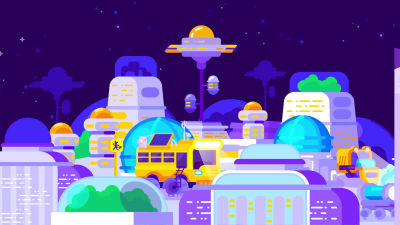何世代も先の未来を守る「長期的思考」を行うための6つのポイント

目の前の問題だけを考えるのではなく、何十年、何百年先を見据えて物事を考える「長期的思考」は、人類の発展や環境問題の改善を計るうえで重要な考え方です。長期的思考で物事を判断するために何を踏まえるべきかを、哲学者のローマン・クルツナリック氏が解説しています。
Six Ways to Think Long-term: A Cognitive Toolkit for Good Ancestors — Blog of the Long Now
https://blog.longnow.org/02020/07/20/six-ways-to-think-long-term-a-cognitive-toolkit-for-good-ancestors/
◆1:人類は地球の歴史において小さな存在であると理解する
新人類が誕生してから約20万年は、宇宙においてほんのわずかな時間であることを認識するべきだとクルツナリック氏は述べています。作家のジョン・マクフィー氏もまた、「地球の歴史を、腕から手の先までの距離だと考えてみてください。やすりで中指を少し削っただけで、人類の歴史は消されてしまいます」と語りました。
地球には人類誕生以前に長い歴史があったように、これから訪れるであろう未来にも長い時間があります。長期的思考では、自分の寿命をはるかに超えた未来で「自分の行動がどんな結果を生むのか」を、生物界の長期的なサイクルに基づいて考えます。「人類は数世紀という信じられないほど短い時間の中で、何十億年もかけて進化してきた世界を独善的な技術によって危険にさらしています。私たちは、生物の大きな連鎖の中ではほんの小さな存在に過ぎません。私たちが生んだ技術が、すべての生態系を危険にさらしています。私たちには、未来の人間や他の種の世代のために、惑星の未来を守る義務があるのではないでしょうか?」とクルツナリック氏は問いかけています。

◆2:後世に何を残すかを考える
人間は、大都市を建設した人々や重篤な病気を治せる医学的発見をした人々など、優れた先人たちから多くの遺産を受け継いで生きています。一方で、植民地や奴隷制度によって人種差別や偏見を後世に残した悪しき先人も存在します。良くも悪くも先人に学び、「将来の世代に何を残すのか」という問題を考えることもまた、長期的思考の1つです。
課題は、子孫や財産を超える「何十年、何百年後に生まれてくる人々のためになるもの」を残すことです。多くの人々が未来に生きる人々に何かを残すための行動しており、例えば、アーティストのケイティ・パターソン氏が2014年に開始したアートプロジェクト「フューチャー・ライブラリー」では、「100年後の読者のために本を書く」という目的のもと、1年に1人の作家から作者自身を除いて誰も読んだことがない作品を集めています。提供された作品は2114年まで未公開のまま保管され、2114年を迎えた際にはプロジェクト開始時に植えられた1000本のオウシュウトウヒから作った紙を使って本が印刷される予定です。
2004年にノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ氏もまた、未来の人々のことを考え行動した人物。マータイ氏は1977年にケニアで「グリーンベルト運動」を立ち上げ、2011年に亡くなるまでに2万5000人以上の女性に林業の技術を教えました。グリーンベルト運動は記事作成時点でも続いており、40年以上の活動で5100万本を超える木が植えられています。

◆3:何世代も先の幸福を考える
過去5万年の間で、約1000億人の人々が生き、そして死んでいると推測されています。そして、2020年における世界の人口は約77億人で、将来さらに人口が増加する可能性があります。21世紀の出生率が維持されれば、次の5万年間で6兆人以上もの人々が生まれ死んでいくことになります。「未来に生きる6兆人以上の幸福を無視できるほど、私たち自身に大きな価値があると考えることができるでしょうか?」とクルツナリック氏は問題を提起しました。
何世代も先を見通す考え方は、アメリカンインディアンであるラコタ族に伝わる「7世代先の子孫の将来を考え生活する」という倫理観にも現れています。また、世代を超えた生活の考え方は、アメリカで子どもたちの法的権利を求める非営利団体「Our Children's Trust」や日本のフューチャー・デザイン研究所の活動などでも広まりつつあります。

◆4:寿命を超えたプロジェクトを考える
「Cathedral thinking(大聖堂思考)」とは、中世の建築家が「自分の人生で大聖堂が完成する可能性は低い」と知っていながらも大聖堂の建築に取り組んだことに由来する言葉で、寿命を超える何十年、何百年にもわたる時間をかけたプロジェクトに着手することを指します。
歴史上、大聖堂思考は大聖堂以外のさまざまな事業や運動にも見られます。クルツナリック氏は例として、1858年にイギリスで発生した大悪臭の後、公衆衛生への関心が高まり地下下水道が建設されたことも1つの大聖堂思考であると述べました。また、19世紀末から20世紀初頭にかけてイギリスで女性の参政権を主張した「サフラジェット」のような、長い時間軸を持つ社会的・政治的運動も大聖堂思考に当てはまります。環境問題への取り組みにも大聖堂思考は重要視されており、グレタ・トゥーンベリ氏はイギリス議会で行ったスピーチで「気候危機に取り組むためには大聖堂思考が必要だ」と述べています。
しかし、大聖堂思考は利己的な目的に向けられる場合もあります。例えば、アドルフ・ヒトラーは千年王国を作ることを望み、何世代にもわたって子孫のために権力を独占しようとしていました。また、企業経営においては、ゴールドマン・サックスの共同経営者であったガス・レヴィが「我々は貪欲だが、短期的な貪欲さではなく、長期的な貪欲さを持っている」と宣言したことがあります。
クルツナリック氏「大聖堂思考だけでは、将来の世代の利益を尊重する長期的な文明を創造するには十分ではありません。大聖堂思考は世代を超えた正義や目標など、他のアプローチから導かれる必要があります」と述べています。

◆5:社会の変化を想定する
以下の図は文明の変化を大まかに3つに分けグラフ化したもので、クルツナリック氏はグラフから文明の変化を予測する長期的思考の重要性を説いています。グラフでは「破綻(Breakdown)」を赤、「改革(Reform)」を黄色、「変革(Transformation)」を緑の曲線で縦軸はそれぞれの変化が占める割合、横軸は時間、青い点線は人々の混乱度合を表しています。

長期的思考を行う上で、「破綻」は生態学的・技術的危機への対応に失敗することで発生する変化と考えます。「改革」は政府が主導する理想的な行動で、気候変動などの世界的な危機に対応しているものの、人々の理解を得られないなどの理由で多かれ少なかれ「破綻」の曲線に影響を与える危険性があります。「変革」は、より長期的に持続可能な文明に向けて、社会の価値観や制度が根本的に変化していく様子を表しています。
「混乱」の曲線は、「改革」が「変革」へ移り変わるきっかけとなるもので、変革が増加する前のタイミングで増加します。例えば、ブラック・ライヴズ・マターのような政治運動の台頭や、新型コロナウイルスのようなパンデミックが当てはまります。
「混乱」は予測不能な出来事でもあり、長期的思考をするにあたって未来で予測不能な事態が発生する可能性を捨てることはできません。「予測不能な出来事があるとしてもなお、長期的思考をする努力が必要です。長期的思考をやめてしまうと、いざ人間に重大な危機が襲いかかってきたとき、その場しのぎで対処することになってしまいます」とクルツナリック氏は主張しました。長期的思考を成功させるためには、「混乱」を「変革」へと転換させる、古いシステムに捕らわれない考え方が重要だとクルツナリック氏は述べています。

◆6:惑星の繁栄のために努力する
人間の将来を惑星単位で考えることも長期的思考の1つ。人類の未来を守る方法として、「地球から脱出して他の惑星を植民地化する」という計画もありますが、火星のような別の惑星を居住できる状態にするには何世紀もかかる可能性があります。さらに、他の惑星へ目を向ければ向けるほど、地球の環境保護がないがしろにされる可能性が高くなります。宇宙学者のマーティン・リース氏は「『宇宙に行けば地球の問題から逃れることができる』と考えるのは危険な妄想です。私たちは地球で問題を解決しなければなりません」と指摘しました。
「私たちの第一の目標は、人間が生命を維持できる唯一の惑星、地球の範囲内で生きることを学ぶことです。地球の範囲内で生きることは、ハーマン・デイリー氏のような先見の明ある経済学者が著書『エコロジー経済学』で提唱した『地球が自然に再生できる以上の資源を使わない』という基本原則にも当てはまります」とクルツナリック氏は述べています。

クルツナリック氏は長期的思考を行うための方法を提示しましたが、「6つの方法はどれも、人間の心に長期的な革命を起こすのに十分なものではありません」ともコメント。一方で「多くの人々が共に長期的思考を実践したとき、相乗効果から長期的思考が新しい時代に結びつく可能性があります」とクルツナリック氏は語っています。
・関連記事
環境破壊がなぜパンデミックを生み出すのか? - GIGAZINE
地球温暖化・環境汚染を防ぐために有効な「あまり広く主張されていない10の方法」とは? - GIGAZINE
気候変動の最たる要因は「富」にある、「豊かさはいいこと」という考えから見直すべき - GIGAZINE
地球環境は「もう戻れないところ」にまで来てしまった可能性がある - GIGAZINE
地球温暖化に個人単位で抵抗する20の方法 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by darkhorse_log
You can read the machine translated English article Six points for 'long-term thinking' to p….