「自由に作れる」ということの難しさ、「ガラスの花と壊す世界」石浜真史監督&プロデューサーインタビュー

1月9日からオリジナル劇場アニメーション作品「ガラスの花と壊す世界」が公開となります。原作としてマンガや小説があれば、そのファンの満足するものを作ることでついてきてもらえることが期待できるのですが、オリジナル作品はゼロからの勝負なので、放送中のテレビアニメでもオリジナルの割合はそう多くありません。そんな中で、本作品は「広く一般から原作を募集し、アニメ化する」という、一風変わった作り方が採られています。
そんな作品であれば、携わっている人の苦労も他の作品とはまた違った部分があるはず……ということで、監督を務めた石浜真史さん、アニメーション制作を担当したA-1 Picturesの加藤淳プロデューサー、“原作”担当・ポニーキャニオンの石原良一プロデューサーに、いろいろと話を伺ってきました。とはいえ、「作品世界にどういった設定があるのか……」といった詳しい部分については、劇場で販売されている72Pのパンフレットに充実の情報が掲載されているので、もっと制作時の話や、その他、業界全般の話などを聞いてみました。
劇場版アニメ『ガラスの花と壊す世界』Official site
http://garakowa.jp/
◆「アニメ化大賞」とは?
GIGAZINE(以下、G):
本日は1月9日劇場公開の「ガラスの花と壊す世界(ガラこわ)」についてお話を伺っていきたいと思います。ガラこわは、2013年に発表された「アニメ化大賞 powered by ポニーキャニオン」の大賞作品「D.backup(ディー・ドット・バックアップ」を原作としています。ポニーキャニオンといえば「けいおん!」「進撃の巨人」、石浜さんが監督を務められた「新世界より」など、数々の人気タイトルの映像ソフトの販売を担当している会社なのですが、「powered by ポニーキャニオン」としてこのアニメ化大賞という企画を行ったのはなぜなのでしょうか?

ポニーキャニオン 石原良一プロデューサー(以下、石原):
ポニーキャニオンという会社はレコード会社ですので、いろいろなアニメ作品を預からせていただいてはいるんですが、社内で「自社が原作の作品というものを持っていないな」という流れがあったんです。出版事業では「ぽにきゃんBOOKS」というライトノベルなどを扱うレーベルを立ち上げたりしていて、「原作を作ってみたいね」というプロジェクトの一環として、まずは「原作者を集めてみよう」ということで、一般の方から公募でできればと行われたのがこのアニメ化大賞です。
G:
おお、なるほど。
石原:
他の出版社さんですとライトノベル作品はいろいろあると思うのですが、ポニーキャニオンにはそういう形のある原作がまだない状況です。しかし、他の出版社さんと比べて、ポニーキャニオンには「アニメ化をすることは得意」という秀でた点がありますので、「思いきって、アニメ化する対象を決める企画をやってみたらどうですか」というのを、ニッポン放送の吉田尚記アナウンサーから提案されました。
石浜真史監督(以下、石浜):
そうだったんですか。
A-1 Pictures 加藤淳プロデューサー(以下、加藤):
吉田さん発案なんですか、これ!?(笑)
石原:
そうなんです、アニメ化大賞の公式サイトで、大賞受賞作品の審査員コメントを見ていただくと、吉田アナウンサーの名前の横に「『アニメ化大賞』企画」と入っております。
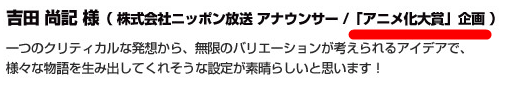
ポニーキャニオン上層部との雑談中に「ポニーキャニオンさん、アニメ作るの得意だから、アニメ化大賞をしちゃえば良いんじゃないですか」という話を吉田さんがしたところ、みんなが真に受けてやってみることになった、というのが事の起こりでございます。
マンガ・ノベル・イラスト・音楽などアニメ化の原作を募集する「アニメ化大賞」作品募集開始 - GIGAZINE

G:
おぉー……形になってしまうというのがすごいですね。
石原:
ちょうど「原作が欲しいよね」という流れや社内の状況ともマッチしたのかなと思います。
G:
アニメ業界のお話を伺っていると、雑談や飲みの席で大事な話がスパッと決まっていたりするそうなので、アニメ業界らしい形で誕生した賞なのかもしれませんね。
石原:
そうかもしれません(笑)
G:
このアニメ化大賞、今回、ガラこわは劇場アニメになりましたけれど、最初から「アニメ化」というのは劇場アニメ化のことだったんですか?
石原:
いえいえ、そこまでは考えていなくて、いろいろな状況が相まって、今回は劇場でやってみようということになりました。
G:
最初の時点ではテレビシリーズやOVAになっていた可能性もあったのですか?
石原:
ありました。フォーマットは特に決めておらず、「大賞が決まってから考えよう」と。そして考えてみた結果が、今回の劇場アニメーションです。

G:
なるほど。Rooftopに掲載されていた石浜監督のインタビューで、監督に話が来たのはポニーキャニオンからA-1 Picturesに制作依頼があって、そのあとだったと書いてありました。最初から「ポニーキャニオン×A-1 Pictures×石浜真史」ありきだったわけではなかったんですね。
石原:
そうですね。
石浜:
それはなかったですね。
◆なぜA-1 Picturesが制作を担当したか
G:
A-1 Picturesさんに制作依頼したのも、大賞が決まってから、と。
石原:
はい。
加藤:
そういえば、何でうちになったんでしたっけ?
石浜:
決め打ちだったんですか?
石原:
これは私ですね、今回、アニメ化大賞の審査員にA-1 Picturesさん、J.C.STAFFさん、Production I.Gさんが入っていたので、「制作するならこの3社だよね」ということは絞られていました。

加藤:
その審査員のチョイスはどこからですか?
石原:
やはり、アニメを作ろうというのだから、アニメを作っている人たちに入ってもらって見てもらったほうがいいんじゃないかという提案がありました。
加藤:
ニコニコ動画だったかYouTubeだったかで、審査員の人たちが集まっているのを見ましたよ。
石原:
AnimeJapanで発表会をやりました。吉田尚記さんが司会をして、それっぽい正装を着て。
加藤:
グッスマの安藝さん、I.Gの石川さん、JCの松倉さん、ニトロプラスの小坂さんとか集まって。あとは、今はアニプレックスに行ってしまったけれど、植田さんが当時A-1 Picturesの社長だったので、会社で放送が流れていたはず。
G:
企画をジャンル不問・応募資格無制限で募集して、その原作をアニメ化するというのはこれまでになかった試みなのではないかと思いますが、何かモデルや参考にしたものはあるんですか?
石原:
特にないんじゃないでしょうか。「ラノベ大賞」のように、フォーマットの決まっている賞は多かったんですが、フォーマットを決めてしまうと同じような才能しか集まらないかなと思って、あえて広く設定してみました。

G:
広かったですよね。ノベル・シナリオ・プロットやマンガはわかるんですが、イラストや音楽でもOKと。
加藤:
思い切ったことするよねぇ。
石原:
本当ですよ。私たちは現場チームなので、決まってから作業をやるわけなんですが。
G:
今回大賞だった「D.backup」のようにシナリオやプロットみたいなものがやってくると「なるほど、順当に分かりやすいのが来たな」という感じだったんでしょうか。
石原:
最初は社内で及第点だったものを上程していくという形で進めて、最終が10作品~20作品ぐらい残っていたんです。そこから審査員の方々に見てもらって、3作品ぐらいに絞って「どれにしようか」と話をした結果、一番アニメっぽくなりそうな作品に白羽の矢が立ちました。他の作品は実写でもできそうな作品だったんです。あとは、ギャグコメディっぽいものと、シリアスで世界観の大きいファンタジーっぽいものでしたね。
G:
ガラこわもすごく広がりのある設定を持っている感じがします。
石原:
「ガラこわ」の原案の「D.backup」は、いい意味で、「知識の箱の中の世界でアンチウイルスソフトウェアが活動している世界」というぐらいしかなかったので、アニメスタッフさんの力でどんどん世界観を広げてもらって今に至っているのかなと思っています。「想像がつきづらい世界」で、どんどん付け足していけるのは良い方向での「アニメ向き」だと思って、今回、大賞に選ばれました。
「アニメ化大賞」大賞作品が「ガラスの花と壊す世界」として2015年劇場公開予定 - GIGAZINE

加藤:
なるほど、そうだったんだ。
◆加藤プロデューサーの「ガラこわ」第一印象:何ともわからぬ「種」
G:
A-1 Picturesの公式サイトに、加藤プロデューサーのお仕事として「GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ」「ソードアート・オンラインⅡ」「ガリレイドンナ」が挙げられています。こうした作品を手掛けてきたプロデューサーとして、「ガラこわ」を手掛けることになった時の第一印象は、他の作品と比べてどんなものでしたか?
加藤:
印象ですか……正直なところ、「どうするんだろう、これ?」という感じでした。たとえば「ソードアート・オンライン」であれば小説がありますけれど、この作品はメディアとして1つの原作の完結系ではなく、いわば、「企画書にテキストベースのシナリオがついてきた」というものなので……悪く聞こえるかもしれませんが、若干、中途半端なものではあったんです。
石浜:
企画としては、そういう感じだよね。
加藤:
逆に「どういう風に作れば良いのかな」というのが率直な感想です。原作があれば「基本はこの通りに作ればいいんだな」とわかりますし、原作のココを忠実に再現しようとか、そういう至極真っ当な考え方になるんですけど、漠然とした「種」が1個あるだけなので、それをどう育てていくかはこちら側次第なんです。そこには、良くも悪くも、難しさがあるので、本当……「どうするんだろう」でした。
G:
今おっしゃった「種」という表現がすごく分かりやすいですね。原作のあるアニメは、育ち方は違ってもきっと誰かが水をやれば芽を出すのに対して、そもそも本当に水をやって育てる種なのか、水をやってはいけないものなのかすらもわからない種を手にしたところから始まっている。
加藤:
そして、変な言い方になるかもしれませんが、我々は依頼を受ける側で、この企画を選んだ側がいるわけです。この漠然とした種を大賞に選んだ人たちがいる。すると、私は、その人たちは一体、この種でどういうものを描きたいと思っているんだろうかと考えてしまうんです。ところが、最初に言われたのは「自由に作ってください」と。
G:
おおっと……。
加藤:
ある程度、最低限のコアがあるとしても結局は作品の種でしかないので、「育て方はご自由に」ぐらいの振りを受けたので、どこに何を持っていこうかというところが一番大変だなと悩みました。何だか、いろいろと考えてしまうんですよ。たとえば、石原さんはどういう風に育てたいんだろう、あるいは、企画を選んだ審査員たちは、何をもって、どう育てたいとか、何かあるのだろうかとか勘ぐってしまう。
石浜:
知りたいよね。
加藤:
きっかけがなかったから、知りたいんですよ。急に種を渡されて「育てて良いですよ」と言われても、「うーん……この種、何なんだろうって。

石浜:
ポニーキャニオンさんがあの企画をどう扱いたいのかをひたすら探る、という日々があった気がしますね。原案をどこまで、どう活かすかとか。
加藤:
「自由に作る」って、本当に難しいんです。作品というのは、どこかに誰か「やりたい人」がいたりして、そういう人たちの思いを間接的に受け取って作ることが多いんですけれど、自由に作るときは自らが発信者じゃないとなかなか自由に動けない、「難しさ」があるんです。言い方を変えると「プレッシャー」とも言えます。「自由に作ってくれ」と言われると、考えてしまうんです。
石浜:
誰の自由かという問題なんだよね。
加藤:
種は用意されているけれど、どう作るんだろう、と。僕の立場で言うと、普段、石原さんが中心になって考えて持ち込んでくれているので、「どういうものを石原さんは作りたいんですか」というところに考えていくしかなくて、それと、監督である石浜さんも作りたいもの、さらに僕もいろいろ思うことがあれば、とか、そういう感じで育てるための方向性を定めていきます。とにかく何を作れば良いんだろうというところが一番難しかった。
石浜:
それこそ、種は若干発芽しているけれど「何なら芽は取っちゃって良いですよ」みたいに言われているぐらいの自由さでした(笑)
加藤:
言い過ぎかもしれないけれど「無茶ぶりするなぁ」と(笑)
石浜:
でも、すごく良い経験になりました。メーカーさんからの押しつけというのかな(笑)、そういうのがないというのはあまりないことなので、現場も育つ良い機会だったと思います。「売らなきゃいけない」という大前提がある中での自由というのは、本来、現場はあまり考えたくなくて、「現場は現場でベストを尽くします」という図式が多いんです。今回はちょっと違う形だったので、加藤くんは相当プレッシャーだったと思いますよ。
加藤:
僕は考えること自体は嫌いではないので、ただ大変だなと(笑)。最初に戻ってしまいますが、「どうしようかな……」というのが率直なところでした。
G:
例えば、原作本とかがあれば、「じゃあ、こうやろうかな」と早めに転がっていくものですか?
加藤:
楽とは言いませんけど、やっぱり明確なものはあると思います。原作のターゲット層も見えているし、ある程度スキームが決まっていれば方向性は見えてくるので、後は何をやっていくかを決めていけばいいだけです。内容については「原作」という回答が提示されている以上、そこに対してアニメとしての答えをどう出していくかというものになりますから。

G:
ふむふむ。
加藤:
原作モノの作り方は「引き算」だと思っています。引き算をしながら、どこにプラスを入れていくかなんです。ところが、今回の場合は「引き算」ではなく、まず式を作らなければいけない。原作モノでも、1を2にする作業は楽なんですが、0を1にする作業は本当に大変なんです。でも、だからこそ、その難しさにこそ本来のクリエイティブの面白さがあるんだと思います。
僕が言うのもなんですけれど、本当に「アニメ化大賞」はプロジェクトとして、「ポニキャンさん、こんなにハードルの高い仕事をよくやるなぁ」というのが本音です。でも、そういう面倒くさい話を抜きにして考えれば、本来はやっていかなくちゃいけないことなんだろうと、仕事をしていていつも思います。昨今の原作モノは続きものも多くて、自分がやっている作品にも4期まで続いている作品があります。それはそれで、ビジネスとしてすごいことであり、とてもありがたいんですが、ただ反面……何だろうな?作品がいっぱい増えていて、とげのある言葉に聞こえたらすみませんが、「既視感のある作品」が多いんじゃないかなと思ってしまうんです。
G:
すごく、わかる気がします。
加藤:
本当は自由に、「マーケティングが」とかではなく、挑戦的な作品をみんなが作っていける余地があれば、そこからまた何か突然変異が生まれて、ブームが広がったり、アニメ業界の活性化に繋がったりするんじゃないかなと。そこで、ポニキャンさんがこういうことを率先してやることは、すごく挑戦的で、すごいことだと思います。僕からは「ぜひ、頑張って続けてください」としか言いようがないんだけれど(笑)
◆石浜さんが監督をやることになったのは?
G:
この難しい作品を石浜さんがやることになったわけですが、石浜さんが監督を任せられた理由というのは何でしょうか。

加藤:
直接的なオーダーではなくて、現・代表取締役社長の落越友則さんと石浜さんが話をしたと聞いています。実は、僕もそんなに知らされていないんです。
石原:
私も、A-1 Picturesさんから「石浜さんでいきたい」というお返事をいただいたので……。
石浜:
僕が落越さんと話していたときの印象は「やっと石浜にやらせたいタイトルが来た」という感じでした。A-1 Picturesでアニメ化するタイトルについては随時教えてもらっていて「はまりそうなものがあったら石浜さんにお願いしますよ」みたいなことを言われていたんです。でも、良いタイミングではまるものがなくて、一方で「これは良いんじゃないか」というものが意外と上手く回らずに立ち消えになっていったりする中で、このポニキャンさんからのお話が来たので僕に振ったんじゃないかなと。
G:
そうなんですか。
石浜:
はい。うまくはまる今回の企画があったので、僕に提案したんだと思います。もちろん、こちらも選ぶつもりは全然なかったですよ。でも、この企画は「とにかくアニメ化する」という前提しかないような状態で、どこに向けて何のアニメを作るのかという情報も何もかもなくて……映画なんて、はじめは一番遠いところだった気がします。

G:
石浜監督が話を聞いた時点では「とにかくアニメにするんだ」ということだけ、と……。
石浜:
そうですね、「アニメ化する」ということと、あとは「この原作をそのままアニメ化するわけではない」とか、そんな感じでした。
G:
かなりぼんやりとした感じですね。
石浜:
なので、「やっておこうかな」という感じの受け方でした。
G:
いやー、すごいスタート地点からこうしてゴールまでやって来たんだなという感じがしますね。
石浜:
そうですねぇ。
G:
こうして「監督やってみない?」と言われたときは、期待と不安、どちらが大きいですか?
石浜:
どっちかというと期待です。僕はすごく楽天家なので、「どう楽しめるかな」とか「どう面白くできるかな」というのが先に立つんですよ。作っていく内に不安になっていくので、最初の第一印象としては期待とか楽しみの方がはるかに大きいですね。作るだけなので、加藤くんみたいにどうしようと考える必要がない。
加藤:
僕は石原さんに文句を言われないためにどうやろうかと考え……
石原:
何を言っているんですか、私も「どうしよう」と思いながらお願いしているんです(笑)
◆加藤プロデューサーのモノ作り
加藤:
僕としては、最終目的として「ユーザーの満足度を高める作品を作る」というのがベストだと思っているんです。でも、僕が直接ユーザーに届けるわけではないので、まずは相対している、今回で言うならメーカーであるポニーキャニオンさんにまず満足していただけることが、最終目的であるユーザー満足度に繋がるという図式で考えているので、まずは目の前の石原さんが満足するものかどうかというのは考えながらやらなくちゃいけないわけですよ。内心は僕もビクビクしながら(笑)
石浜:
それぐらい強気の姿勢だから助かった、すごいありがたかった。加藤さんは現場をたった一人で当時守っていて、石原さんからいろいろな攻撃が来るんですよ。それを全部弾いて、現場まで届かないようにしてくれていました。

石原:
私もそういう立場なので!(笑)
G:
作品内と同じように、ここにもすごいバトルが……!?
石浜:
バトルというか、要求に対して現場がどこまで飲めるかというきちんとした査定を加藤くんがしてくれるという感じでしたね。
加藤:
いろいろなことを考えないといけないですもんね。
G:
それらを任せている石原さんからすると、どんな感じでしたか。
石原:
加藤さんは安心のプロデューサーです(笑) すごくちゃんとしているなと思ったので、特に不安などはありませんでした。ただ、こちらから無茶ぶりで後からいろいろ投げてしまったなと。
加藤:
そういうひらめきはすごくプラスになるので、できるところに関しては汲み取りたいと思っています。さすがに、全部は反映できなかったですけれど。こうして「言われること」自体はとてもいいことで、一番まずいのは「何も言われなくなる」ことだと思っています。
石原:
「依頼を投げて、お金を出して、終わり」みたいなことですね。
加藤:
それはたぶん、一番しんどいでしょうね。最終的にこちらができるかできないかによって落とすものも出てきますが、言っていただけること自体はありがたいです。
G:
なるほど、全部が全部「無茶」というわけではなく、光るものもあるわけですよね。来たら、まずは揉んでみるというか。
加藤:
そういうものだと思うんですよ。スタッフさんともよく話すことなんですが、立場が違うと利害関係もあって、関わり方も変わってきます。でも、「作品を良くしよう」というベクトルがお互いに一緒だったら、どこかに落としどころはあるはずなんです。もし、ベクトルが正反対ならこれは無理だとなりますが、同じ方向、あるいは近い方向を向いているなら、ぶつかっている部分は立場の違いであるはず。一歩引いて、最終的にこのプロジェクトについてできる範囲内のベストは何かと考え、「じゃあ受けようかな」とか「申し訳ないですけどここは無理なんですよ」とか、そういうイメージで動いています。軽口で「辛いこと言われましたよ~」とか言いますけど、そんなに悪い意味じゃなくて、本当にそういう感覚でやっていただけた方が個人的に僕もすごく助かるなと、いつも思っています。
G:
ぶつかっているのではなく、いかに良くするかのところのせめぎ合い。
加藤:
そういう風に持って行くべきですよね。もちろん感情的なことも受け入れる可能性もあると思うんですけど、それも「次に行くための必要な儀式だったのかもしれない」ぐらいの感覚を持たないと、モノ作りなんて基本できないんです。昨今は効率化をみんな求めるから、リテイクや戻るということを気にする人が多いんです。それはコストがかかるから仕方がないんですが、そもそもモノ作りはトライアンドエラーだから、どうしてもそういう思いつきとかも出てきます。でも、その思いつきのようなトライアンドエラーをNGだと、やっちゃいけないというのはモノ作りではないと思ってしまって。
G:
はい。
加藤:
理想論ですけれど、そういうことが起きても途中で受け入れられるような余裕を作っておくとか、そういうことを考えながら現場を作っていかないと、本質的に良い物はなかなか生まれないのかなとか……もう一人で小難しいことをずっと考えてしまうんですよ。

◆原作者も納得の「ガラスの花と壊す世界」
石浜:
加藤くんはいろいろなタイトルでいろいろな人と当たっているから。
加藤:
すべてがすべて、上手くいくわけではないですから。
石浜:
でも、「ガラこわ」は基本的に全部プラス向きのやりとりだったので、しがらみとかは一切無かった気がします。ポニーキャニオンとA-1 Picturesでしかないですしね。なので、「良い物にしよう」というみんなの欲望みたいなものがワーッと盛り上がったことはあっても、マイナス方向のものは、僕のいる立ち位置では一切見えなかったですね。他のタイトルではマイナス要素は山ほど降ってきますから。例えば……いや、これはやめましょう(笑) 「ガラこわ」では、一切そういうことがなかったです。
石原:
原案の方もご満足いただいています。
加藤:
むしろ、こっちが気を遣ったぐらいです。「良いの!?良いの!?」みたいな。

石浜:
「もっと言わなくていいの!?」というね。
加藤:
「大賞取ったんでしょ!?」ってね。
石原:
「我々は全然大丈夫です」と。
石浜:
あまりにも返事が早いので「本当かなぁ」って(笑) 自分が応募して大賞を取ったものが「あれ?使われてない……」ってなると切ないじゃないですか、それは同じ作り手なので気にするんですよ。だけど、石原さんの中では勝算が別のところにあったので、そこじゃないという。
石原:
原案の方には、今回の「知識の箱」とかの設定を活かしつつ、「リモ」というキャラクターを共通させるので、後は自由にやらせてくれという話をかなり最初にお願いをしていたので、大丈夫でした。
リモ(CV:花守ゆみり)

デュアル(CV:種田梨沙)

ドロシー(CV:佐倉綾音)

石浜:
石原さんは「自由、自由」と言いながらも、こう見せたいというのはちゃんと持っていたのは確かなんですよ。局所的な部分ではあるけれど、作りたいものはわりとはっきりしている、でも、ぼやっとしている部分もものすごくたくさんある企画というだったので、それを探っていく感じで……ただ、「自由と言ったから!」という人なので、答えを言わないし、探りにくかったですよ(笑)
G:
ぽにマガに掲載されている「リモのはこにわ」には、映画にはいるデュアルとドロシーは出てきていません。でも、確かに「ガラこわ」の世界の1つだと感じます。
石原:
たぶん、いろいろな知識の箱があるんですよ。
加藤:
設定がそういう感じのイメージですよね。デジタル世界のキャラで、プログラムだから、それこそ「リモ コピー1」とかあっても全然おかしくないし、リモが100人いる可能性もある。ネガティブっぽいけれど「改ざん」といか、いろいろなネタも突っ込める。
石原:
設定の拡張性が高いんですよね。彼女たちの言っていることも本当かどうか分からないので、何でも広がり続けるというあり方なんです。
加藤:
今回のアニメのフィルムとかも見ていて思ったのが、3人の出会いと別れは一貫して描かれているけれど、世界観の説明とかはボヤッとしたままのところもあったり、あるいは広がりが可能な隙が所々にいっぱいあったりする。言い方を変えると、世界を簡単に広げられるというか。
石浜:
説明しなくても良かったけど、ぼやぼやとふわふわっと絡ませてしまっているので、余計にそういう印象になっているんですよね。
加藤:
そうすることで、ポニキャンさんがいろいろなメディアで世界を広げていく中での繋がりみたいなものが、むしろ逆に見えやすいのかなと思う。
石原:
企画が結果的に良い形になっているのかなという気がするんですよね。
加藤:
世界観の拡張性の高さは、言い換えるとこれという決まりがなくてぬるくもあるんですが、そこを上手く利用している感じがします。

石原:
本当にキャラクターもの、キャラクターがどれだけどう見えるかというところに重点を置く作品だと思っているので。そのための脚本・志茂文彦さんとキャラクター原案・カントクさんですし。
G:
志茂さんは現在、月刊ニュータイプに「白昼夢変奏曲【デイドリーム・ヴァリエーションズ】」を連載中ですね。本編のアナザーストーリーで、リモ、デュアル、ドロシーが登場しています。これも、世界を広げる作品で、映画では描かれていない部分は実はこうなのではないかと空想する余地が多くて、いろいろ考えたくなります。
加藤:
さっきの小説とかいろいろなメディアを全部ひっくるめてバーッと見てもらいたいなという気持ちがあります。もちろん、僕らとしては作ったアニメをぜひ見ていただきたいと思っていますが、それだけではなく、他のメディアで展開されているものも横断することで、世界をより楽しめるのではないかと。

石原:
各々が良い感じで外向きのベクトルになっている感じがして、もちろんPhysics Pointのお二人の作ったものが本物の「D.backup」なんですが、それぞれにきちんと重さがあるメディア展開はなかなか少ないのではないかという気がしています。原作があってアニメ化したというのとは根本的に違っていて、どれが中心ということのないメディア展開は、僕が見ていてもすごく面白いですし、上手いなと思いました。
石浜:
コミカライズに関しては、劇場アニメのコミカライズなんですよね。
石原:
G'sコミックさんのものはそうですね。
石浜:
そのあたりは、やっぱりポニキャン上手いんだなぁと思うし、石原さんが営業に強かったというのも大きいですね。アニメプロデューサーの才能もあるけれど、営業の才能も元々のスキルが高い。
G:
石原さんといえば、ポニーキャニオンの名物広報さんでしたね。
石原:
そうですね、「エコロジ」を名乗って、抱き枕を持ったりして(笑) 訳分かんない系でしたけど、とにかく、宣伝活動になればいいかと思ってやっていました。

石浜:
ものすごく重要なことですよ。やるのとやらないでは反応が大違いなので。
石原:
でも、こうして制作になって思うのは、宣伝のスキルだけではアニメは作れないということですね。
G:
宣伝からプロデューサーというのはやっぱりあるんですね。
石原:
メーカーでは比較的あって、宣伝から入って制作になられるという方も結構多いです。
加藤:
アニプレックスさんにも何人かいますよ。それはそれで、スキルが役立ちそうですよね。
石浜:
タイトルによってはスキルが生きます。今回は特に宣伝がいかに重要かというタイトルだったので。「誰も知らない」は言い過ぎかもしれないけれど……。
G:
「あの有名原作を!」というわけではないですもんね。
石浜:
そうなんですよ。なので、宣伝がどれだけ大切かというところがあるんですけど、上手いなぁと。
加藤:
仕掛け方はメーカーさんらしいなと思いました。例えば、ガンダムなんて、監督もキャラクターも違っていても「ガンダム」という名前が引き継がれていくのは、ファーストガンダムがしっかりとコアになっているからです。ガンダムで例えてしまうと大げさになってしまうけれど、リモや知識の箱をコアとして、今回のようにアニメやコミックや小説が展開できるし、それこそ学園モノにもできるし、アクションモノも作れる。「ポニーキャニオンとして原作を作りたい」みたいなことも含めて、そういう壮大なスキームなのかな、そこまで投資するんだろうかとか考えてしまいます。

石原:
行けるならそこまで行ってみたいですねぇ。
G:
そうやって聞くと、見つけたのはものすごい光り輝く種だったのかもしれませんね。
◆石浜監督の仕事
G:
石浜さんといえば、映像化不可能と言われていた「新世界より」の監督であり、「ヤマノススメ セカンドシーズン」、「SPEED GRAPHER」、OVA「てなもんやボイジャーズ」など、「石浜OP・EDだった」と注目されるアニメーターなわけですが、今回、石浜監督がアニメーターとして作業したパートはありますか?
石浜:
いわゆるアニメーターとして担当している場所というのはないんです。あくまで監督としてのチェック上で、アニメーターとしてのスキルを振るっているというだけなので、しっかりと僕の担当パートがあるという参加の仕方はないですね。ただ、今回アニメーション作りにおいて、他の人に任せられない部分のレイアウト作業を拾うというのがあったんですけど、それはアニメーターとしての参加の仕方とは違うので、絵に関しては作画の人たちに任せていましたね。

G:
レイアウトで他の人に任せられない部分というのは、どういうところだと任せられないというのがあるんでしょうか?
石浜:
自然の景観とか、圧倒的な美しさとかというのは、他の人に依頼すると、その人なりのものをしっかりと示してくれるんですけれども、自分と違う答えが来るとそれはもうゼロになってしまうんです。自分の思う感動できるものと合わないと、作業自体が無駄になってしまうので、最初からこっちで引き取ろうというやり方でした。アニメーションでいう、普通の組み立てていく中でのカットのレイアウトというのは答えがたくさんあるんですけれども、僕が思っている「ここで感動する絵が見せたい」という答えはやっぱり一つになってしまうんですよ。今回は統一したいというのもあったので、そういうところを拾ったという感じです。
G:
なるほど。今回、スタッフの方々はいかがでしたか?
石浜:
世界観的に、進撃の巨人のオープニングで組んだ、美峰の吉原俊一郎さんとやりたいとお願いしました。また、竹内志保さんにも入っていただいて、力を貸していただくことができましたね。
◆世界コンセプトデザイン・六七質(むなしち)さん
石浜:
今回、「世界コンセプトデザイン」を担当してくださった六七質さんは、純粋に僕がファンでファンで大好きで、ずっと絵を愛でていたんです。今回、この「ガラこわ」という企画で、お願いできるとなって、加藤くんにちらっと漏らしたら、すぐに。
加藤:
六七質さんは背景イラストレーターで、僕も全然お付き合いがなかったのでどうかなぁと思ったんですが、検索するとご本人のサイトを見つけて、問い合わせ先が載っていたんです。なので、さっそく「私、このような者ですが、お話だけでも聞いてもらえませんか」とメールを打ったら、すぐにお返事をいただけて、会って話をさせて欲しいと、ばばーって話をしたら「何とかなりそうなので、やります」と言ってくれて。
石浜:
とんとん拍子に話が進んだ上に、しっかりと興味を持ってもらった上で呼んできてくれたので、ありがたいなぁと思いましたね。
加藤:
もう、聞くしかないですもん。興味がないんならしょうがないし、時期が合わないもあるかもしれないので、もしよろしければ、と。
石浜:
でも、興味津々の前のめりな感じで来てくれましたね。もともと「目一杯楽しみますよ!」という感じなのかもしれませんが、そこもすごくありがたかったです。
加藤:
アニメのこうしたデザインみたいなものは初めてだと言っていました。
G:
意外な人を連れてくることができたんですね。
石原:
普段は挿絵やゲームの背景・設定などがメインみたいな感じだそうですよ。
加藤:
「独特の感性」みたいな感じで、またどこかでご一緒できないかなということは、いつも頭の隅にあります。
石浜:
仕事が速いのもいいですよね。
加藤:
速いですね。
G:
「ガラこわ」制作では、出てくる人たちがみんな、作品をいい方向へ向かせようとしてくれる人ばかりですね。
加藤:
何もないなかで作っているような感じですから、そういう時には力がよく働くのかもしれません。自由にやっていい、というのはなかなかないですから。
石原:
実際、個性が出せる場というのは少ないよね。
加藤:
個性を出すのが好きな人にはとてもやりやすい場だったと思います。六七質さんにもほとんど制約なしで「何でもいいから、とにかく思いついたものを描いてきてください!」みたいな。

一同:
(笑)
加藤:
最初はちょっと乱暴とも思える発注をしたんですよね、「こういう感じな」ぐらいの、本当にざっくりしたイメージしか伝えずに。
石浜:
そうそう。石原さんのことは言えないですね(笑)
加藤:
だって、ああいうのはブレストですよ。極論でいうと、使えるか使えないかも含めて関係なく、面白いアイデア、イメージ、ビジュアルみたいなものをとにかく出してくれと。もう、本当に失礼ながら、ラフ画みたいなものでもいいから、面白そうなものがあったら何でもいいから描いて送ってくださいと。そうすると、「これはどうですか」「こっちはどうですか」と、すごいポテンシャルの人だったので……いろんなものをポンポンポンポンとスピーディーに出してきたのは、すごかった。

石浜:
結局、世界観に関しては全採用です。「どうやってそんなの創ってるの?」みたいな感じですよ。
G:
うおお、すごい……。
加藤:
ああいうのが好きなんでしょうね、多分。普段とは違う感じだったんじゃないですか。
石浜:
要求された絵をきれいに描くとは全く別のものを要求したんですけど、そのスキルも卓越した人だったんで。未知数でしたからね。
G:
それが、今回の作品にはピタッと合った。
石浜:
あれは結果としてそういうことなんだろうなぁ。「案外合うな」とか、そういう次元じゃない感じですよ。
加藤:
本当に、オリジナリティをもっていて、ばんばん出せる人ってあまり業界にはいないですよ。言い切ると語弊があるかもしれませんが……。
石浜:
いやー、アニメ業界には、ほぼいない。
加藤:
だから、ゲーム系とが、全然違う分野に行くと、在野で個性的な人がポンといたりする。
石原:
いますよね。
石浜:
いるいるいるいる。

石原:
アニメ業界の中では、やっぱり、見たことがある感じがあったりする。
加藤:
もちろん、そういうものを求めて作っているなら全然問題はなくて、悪くはない。ただ今回は、何者でもない種から映画を作るということだったので、やっぱりそこには何かを織り込みたいと思う。
石原:
今回の作品、世界観とかに関しては私、あんまり私NG出してないんですもんね。別に「自由に」って言ったから我慢したわけではなく、良い感じにはまったんだろうなと思って。「世界観は六七質さんがいいですよ」と加藤さんが、おっしゃったときくらいから、もう任せて大丈夫だと思いました。すごく、この作品のことを前向きにやってくれるんだな、っていう感じがあったので。
加藤:
原作の大体の雰囲気は何か分かるじゃないですか、みんな、こういう雰囲気なんだなっていう。この作品の場合、絶対にこの先で美術が重要だったんですよ。だから、そこだけはしっかりコンセプトを固めておこうと思った。ネットでイラストレーターさんの絵をいろいろ検索して見たりしました。調べた記憶が残っています。
◆それぞれのアンテナの張り方
加藤:
僕は自分で何かを生み出せたりはしないので……できるのならクリエイターになっていますから(笑) だから、アニメとかだけじゃなく、それこそ実写とか、音楽とか、絵画でも何でも、できるだけいろんなものにアンテナを張ってい、ああこれお面白そうだなとか、なるべく引き出しに少しでも入れるようにしています。
G:
アンテナはあらゆるジャンルに向けて張っているという感じですか?
加藤:
理想は、ですけどね。だけど実際はそこまではいけてないです。
G:
このあたりは中心として見ておいた方がいいなと思っているのはどのあたりですか?
加藤:
それはもう、自分の好みになってきますね。ただ、「戦略的に」というと大げさですが、最近、マンガはとんと読まなくなりました。漫画原作とかで仕事をいただくこともあるので「まったく見ない」というわけではないですが、マンガの中からアニメの企画とかを追っかけるのは、僕の立場だと、とうてい専門の企画営業プロデューサーには敵わないなぁというのがあります。
G:
ほうほう。
加藤:
たとえば、メーカーのプロデューサーさんとかの方が絶対に速いんですよ。だって、編集部の方たちともコネクションがありますしね。もっと言えば、原作漫画で一番面白いものを誰が知っているかって、編集者さんですから、その編集者さんとのパイプが強いメーカープロデューサーさんが、「まだあんまり売れていないけど、これ絶対いけるよ」って言ったら、ネゴシエートできちゃうじゃないですか。それが専門職ですから。
G:
確かに。
加藤:
僕らは作品作ってると下手すると半年とか1年とかを1本に集中して、次って感じなので、追っかけるための時間があまりないんです。なので、そこは専門家にお任せしてしまう。反対に、石原さんみたいな専門家が、「これは面白い」って持ってくるんだったら、面白いんだろうと。僕は、それを形作るためにどんなアイデアが必要かを考える方に集中した方がいいでしょう、時間は限られているので。
石浜:
そりゃそうだ。メディアは広すぎてキリがないよね。
加藤:
例えば、「あれ面白いよ」って持ってきてもらったら、知らない作品であれば最初に「面白いところを教えて」って聞きます。それが聞けると、作るヒントになるじゃないですか。
石浜:
そうだね。その人は何が面白くてそれを映像化したくて持ってきたかが分かれば、ヒントというか答えだよね。

加藤:
答えなんです。その答えを、フィルムにどうやって焼き付けていくかにプロデュース方向が見えるので。そうすると、このパートはこんな感じにしようだとか、監督にも「ここはもうちょっとこうやって欲しい」とか、できる。あとはパズルをはめていくような感じ。すると、最初のピースは、この作品を一番面白いと思っている人がはめるべきなんですよ、理想としては。
石原:
うーん、それしかないような気がしますね。
石浜:
今回も石原さんが前のめりだったので、助かったところはありますね。ポニーキャニオンの中で石原さんが「任されて来ました」ではなく、手を挙げて乗り込んできてくれた感じがあって、そこから、答えがもうある状態からスタートできたのが良かったと思います。
◆各人の“インプット”
G:
少し戻ってしまうんですけど、例えば石浜監督だとアニメの絵を描くのはアウトプット作業だと思います。何か自分にインプットする作業とかはなさったりしますか?
石浜:
めちゃくちゃしています。加藤くんじゃないですけど、基本的には実写映画とミュージックPVがほとんどです。漫画はあまり読む方じゃないし、恥ずかしい話、アニメーションはほとんど見ていないので、映像の生理的な気持ちよさとか構図的な気持ちよさとかは全部そこからです。あと、カタルシスの持たせ方のテクニックも全部そこですね。ハリウッド映画はやっぱり上手いです。日本映画とかフランス映画もものすごく好きで見るんですけど、いざテクニックとなると、ハリウッドの上手さは群を抜いていて、はしょり方とか、見せたいところだけ見せる感じとか、アニメーションの武器になることなので、完全にその辺りがインプット対象です。

G:
それは一般的に「あの映画が面白かった」と言われているものと一致しますか?
石浜:
しないですね。何でだろう……。すごく盛り上がっていた作品を家族でみんなで行にいって「へぇ……」ってなって帰ってきたということもあるんですよ。なので、いわゆる市場と一致するかと言ったら、そういう訳じゃない。それは「自分の作りたい物を作るのをベストと信じよう」というところはあるので、みんなが良いって言っているから同じ物を作ろうという脳みそはないんですよ。できれば作りたい物を作りたいし、それが良い物だって信じたいというところは少なからずあります。なので、合わないときは合わないですよね。超絶ヒットする要素はどこだろうと一生懸命考えたけど、やっぱり答えが出なかった作品です。
加藤:
僕は一生懸命分析しましたよ。
石浜:
あれは何なの。
加藤:
正確には分からないです。でも、あの映画の結果を見て何か考えなくちゃいけないんだろうなと。
石浜:
それぐらいのヒットの仕方をしたよね。
加藤:
あれはエンタメ業界の人は絶対に無視してはいけないんじゃない。
石浜:
その答えが、本当は欲しいですが、なんか難しすぎるんです。
石原:
いやー、難しいです。
加藤:
見せ方やテンポは多分、今のアニメの理想型になると思うんですよね。
石浜:
俺もそう思うんだよ。
加藤:
「アベンジャーズ」とかも、話の流れ方やとか、テンポとか。
石原:
感情のテンポとかね。
加藤:
あれはものすごくアニメっぽい。アニメ業界のいろんな人に話を聞いてみても、アニメってどんどんああいった感じになるのかなって思います。
石浜:
だけどね、日本人にはあれがないんだよね。作り手にね。
加藤:
目指す方向としてはあっちの方向に行くんじゃないかと。最近は本読みをやっていても、とてもテンポが意識されているから。「こんなセリフはいらないんですよ」とかね。ちょっと昔のアニメであれば成立するけれども、今ではこのセリフは迂遠で必要ないから切りましょう、テンポなんですよって。結構多いですよ。
石原:
アメコミのようにテンポアップな感じで。やっぱりアメリカのドラマをみんなが参考にし始めましたね。
加藤:
俺も海外ドラマをよく見る。
石浜:
俺も海外ドラマをよく見ますよ。
石原:
海外のドラマはテンポがいいですからね。キャラクターっぽい感じにして無駄な説明を省いている。
加藤:
キャラものなんですよね。
石原:
そうなんです。実は。
加藤:
ほぼ全部キャラもので、普通の人がほとんど出てこないっていうのもポイントだよね。
石原:
結構みんなぶっ飛んでますからねえ。
石浜:
でも、あれはアニメで置き換えられるなって、正直いつも思っていて。
加藤:
だから、そういう風になりつつありますよね。やれているかどうかは別問題として。みんな、狙いはいつもそっちに向かっちゃっている。
石浜:
実写は絵面的にはアニメに置き換えにくいんですよ。実写ではいい絵でも、アニメにすると全く良くない。アニメならではの要素はもちろん追求しなければならないですが、そのテンポは相当参考になりますね。
加藤:
よく言われますよね。俺もそう思いますが。多分飽きてしまうんでしょうね。
G:
どうでしょうか、特に刺さった作品はありますか?
石浜:
何見ても面白いんですけどねえ……つい昨日見てきた「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」はテンポの良さもあるんですが、「スター・ウォーズ」ファンの何たるかを分かった上で出してくる感じが、もうたまらなくて。エピソード1からの新三部作で立ち返ったころのような、また違う「スター・ウォーズ」を見せるのかなって思いながら、前情報ゼロで見に行ったら、ファンムービーだったので、大喜びしてしまって。ここまでかと思いましたね。それこそ、ハン=ソロとかもう出てこないのかなって思っていました。

G:
完全にゼロベースですね。
石浜:
ルークなんて全く出るわけないと思っているのに、行ったら、最後にぬーんって立ってるし。もう、心では叫びまくっていました。映画として、1つの作品として成立しているかというと、僕にはそれは分からないですけど、やっぱり映像作品としてはすばらしいと思いましたね。息子と一緒に吹替版を見に行ったので、子どもがたくさん居たんですが、子どもたちは一切騒がなかったです。要は、子どもが騒ぐようなシーンがないんですよ
G:
ほうほう。
石浜:
大概の映画で子どもが騒ぐシーンっていうのは、映画館に行っていると分かるんですけど、子どもが一切、意識を向こうに持っていかれなくなる瞬間の会話劇とかなんですが、「フォースの覚醒」にはそれがなかったんですよね。会話劇をしないといけないときにアクションをしているんですよ。その辺のテクニックが近年では一番上かなという「アベンジャーズ」ですら、息子がちょっと退屈するっていう瞬間が、幾つかあったんで。ハルクと何だっけ、スカーレット・ヨハンソンの……
G:
ブラック・ウィドウですね?
石浜:
あの2人の関係を説明するところで、子ども達が集中を切らせてしまうんですよ。けど「フォースの覚醒」に関しては、そういったところがない。レイとフィンの人間的なドラマのところも食い入るように、幼稚園ぐらいの子どもでも見てたんで……やっぱり、すごいなあ、J・J・エイブラムスは。
一同:
(笑)
石浜:
やっぱり、ちょっと違うな、視聴者が見えているなっていう感じが、ものすごくしました。誰が見えているのかは知らないですけどね、監督ではなくプロデューサーかもしれないし……。まあ、いろいろ。ちょっと昨日だったんで、記憶が濃いっていうのもあって(笑)。台湾映画の「シェフ」も会話劇と映像の美しさで刺さりましたねぇ。キャラクターに悪者がいるかと思ったら、全員いいやつで。そういうところも好きなんですよね。あの、昔で言うと「特効野郎Aチーム」みたいな。死にそうで誰一人死なないとかっていう、ああいった感覚も実はものすごく好き。予定調和的な優しさが僕は割と好きで、甘いのかもしれないですけど、全員を救っておく感じは嫌いじゃないんですよ。何かそういうところでも、悪役が悪役とし過ぎているのも好きなんですけど、基本的には全員にいい人になって欲しくて。だから、カイロ・レンがハン=ソロを……というところ、あれはしょうがないんですけれど、しょうがないけれど……ちょっと残念だなって。
G:
なるほど。加藤さんも海外のドラマを結構見られるということですが。
加藤:
俺はたぶんまた毛色が全然違うと思うよ。最近見たのはNHKの大河ドラマ「龍馬伝」を、もう4回目ぐらいのローテーションに入っていますね。
G:
おぉ、すごい!ローテーションに……。
加藤:
もうあのドラマ大好きなんですよ。大友さんの作品が昔からすごく好きで「ハゲタカ」とか、「るろうに剣心」はフリーになって初めての映画作品だったけど、もっと渋い方が俺は好きだな。普通に海外ドラマっぽいのとか「ハウス・オブ・カード」とかも見ますけど、気分によるんですよ。
石浜:
あぁ、あるね。
加藤:
こういう仕事をして言うのも何ですけど、僕は映像を見るのにすごい力が必要で、極端なことを言うと、見るとすごく疲れるんですよ。やっぱり何か単純に軽く映像を流して見られないというか。
G:
見ながらもいろいろと考えてしまうんですね。
加藤:
見ようと思うと結構な力と心が必要だから、そのときの気分に合ったものじゃないと見たくなくなるので、結構いろいろ、あるとき突然舞い戻ってくるんですよ。急に最近「龍馬伝また見たい!」という風になっちゃったり。1年間やっているから50本ぐらいあるじゃないですか。今やっと半分ぐらいまで来て、「あぁ、勝海舟と会った。そうか、まだここかぁ」みたいな感じで。
石浜:
僕、アニメ見ないのは疲れるからだ。
加藤:
だから同じですよ。
石浜:
で、俺は疲れるものは一切見ないの。
加藤:
俺、HuluとNetflixとAmazonプライムとかいろいろ活用してる。忙しいから夜中とかに見るんですよね。テレビというよりは配信系です。
石浜:
いつでも見れるようになったよね。
加藤:
そう、「女王の教室」とかも見た。
一同:
おおーっ。
石浜:
これも微妙に古いんだか何だかの微妙なところなんだよね。
加藤:
いや、あれも当時見てたんですよ。
石浜:
分かる。
加藤:
だけど、それは3ヶ月ぐらい前だけど、急に見たくなってそれも1日で見たわ。
G:
うわぁ……。
加藤:
8時間かけて1クール全部バーッと。
石浜:
見れちゃったんだ。
加藤:
そう、夜の10時ぐらいから見始めて、朝の8時ぐらいだったかな。俺が見始めてから嫁さんが寝て、嫁さんが起きたときにまだ俺は見てるという。「まだ見てたのか!?」とか言われて、「いや、ちょうど今最終回」みたいな。何か日本のやつ結構見ますよ。池井戸さんは小説も大好きだから、普通に「下町ロケット」とか楽しみに見てましたし、本当に好きなのを見ていますよ。
石浜:
俺は好きなのしか見ないよ。
加藤:
分かりますよ、だから好きなものもそうだし、後はさっきのアナ雪じゃないけど、世間でこれが受けていますとかはある程度目を通すけど。
石浜:
プロデューサーだから目を通さなきゃいけないからね。俺は一切通さないよ、見たくなきゃ見ない。
G:
石原さんもいろいろ目を通さなきゃって見るときもありますか?
石原:
見ますね。見方が半分以上は分析になっていますよ。

石浜:
分析ですよね、それが嫌なんですよ。分析したくないので、アニメを見なくなってしまった……。
G:
業界の方は忙しすぎて見ている時間があまり取れないという方もいらっしゃいますよね。
石浜:
見たいんですけどね。
石原:
最近はあまりアニメ見てないかもしれない。話題作品以外見てないかも。
加藤:
話題作品もちょっと頭見たら……
石原:
正直、ストーリーのフォーマットは決まってしまっているので、あまり分析するものがないなぁというのは感じられますね。
G:
石原さんは最近見ている作品ではどうですか?
石原:
最近だと遅ればせながら「ブレイキング・バッド」をシーズン5まで見終わりました、あれは名作でしたね。
石浜:
よく見たねぇ……。
石原:
あれは珍しいやつで、シーズンを追う毎に面白くなるんですよ、ダレないという。
G:
すごい。
石浜:
ああいうのをアニメで作れないですかねぇ。
石原:
作ってみたいですけどねぇ。
石浜:
めちゃくちゃお金がかかりそうだけども。
加藤:
俺見てないんだよな……。
石原:
J・J・エイブラムスに脚本を頼んだらいくらかかるんだろうと最近妄想しているんですけど、シリーズ構成みたいな。
石浜:
あぁ、高そうだなぁ……。
加藤:
どのアニメでプロデュースしようと思っても今はそういう発想ですよ。
石浜:
原作の源をどう生み出そうかという感じですよね。
石原:
そうですね、だいたいもう使い切っていますから。
加藤:
まだそんなに売れていないんだけど、面白そうなものをアニメ化と同時にプロジェクトを持ち上げるという手法も多くなりましたね。
G:
まさに「アニメ化大賞」で、原作を1から生み出してもらって、みんなで芽を出そうとやっていくというのが重要なところになってきますね。
石原:
そうですねぇ。うちとしてはリスクしかないので(笑)、そのリスクを許容範囲として認めていって、こういう作品作りが続けていけたらなぁとは現場の一人として思ってはいます。とはいえ会社なので、赤字ばかりだとつぶれるので、そこのバランスは上手く取っていきたいですね。
加藤:
本当にそういう場を作らないといけないと思いますよ。だからこそ、ポニキャンさんがそれをやるというのはハードルも高いと思うし、すごいなと思うんです。
石浜:
一方で、アニメ作りに関する枷が1個、2個ついていると、むしろ燃えるところはありますね。

加藤:
それもありますね、多少の制約があった方がクリエイティブにできる面はあると思うので、うまく作っていきたいです。
G:
このアニメ化大賞は種に例えられた通り、やっぱり芽が出るまではどうしても時間がかかると思います。2013年に発表された大賞作品がこうして2016年1月に劇場公開になりますが、この先も耕していく予定はありますか?
石原:
個人的には耕していきたいんですが、後は会社の判断もあるので、何とも言い切れません。ただ、今回のフォーマットをできれば成功で終わらせて、どんどんいろいろな方とまた作品を作っていけたらなと個人的には思っています……が、まだ特に第2回の予定はございません。
石浜:
「ガラこわ」の答えが出ていないですからね。
石原:
そうですね、「ガラこわ」で答えが出て、ちゃんとヒットしてくれるか、ちょい赤ぐらいならまた第2回、第3回のアニメ化大賞もやりたいです。もう目も当てられない真っ赤だといろいろあるので、そこから先の話が変わってきます。まぁでも現場として、気持ちはやりたいなと思ってはいます。
石浜:
なんかね、そういうところでも違った才能が出てくると。
石原:
今回「ガラこわ」という作品で形が出てることで、次回は応募しやすくなると思うんです。何か、アニメ化大賞ってすごく危なそうな企画だったんですよ。「アニメ化って言ってもどうせ1分とか何でしょう?」という感じでみんな見ていて、「1分でもアニメ化したじゃん?」って終わらせるのではないかと思っていたのではないかと。でも今回、劇場60分という、かなり男気溢れるフォーマットで作ってみたので、次は応募する意欲が増して、さらに多くの方からの応募がどんどん来るんじゃないかなとは感じてはいます。
G:
劇場60分はなかなかですよね。
石浜:
なかなかやっていないところですからね。実際、企画を見たときは短編15分とかでお茶を濁す系と思われるんじゃないかなと思ったんですよ、現場にいる僕ですら。
石原:
意外とポニキャン真剣だったんだなとたぶん感じてくれたと思うので、続けていきたいなとは思ってはいます。
G:
意外どころではなく、大マジのマジでしたという感じですね。
加藤:
夢のある企画だったんですよ。
石浜:
実はアニメ界にとっても、大事なタイトルのはずなんですよね。
石原:
もしこのフォーマットで成功したら、前よりすごく自由にアニメが作れると思うんです。今、テレビフォーマットでがんじがらめなのがアニメ業界なので。
G:
オリジナルで60分の劇場作品が風穴を開けることになるのか、今後のアニメ業界を占う意味でも、ぜひ見ておいて欲しい作品ですね。今回はお三方、長い時間ありがとうございました。
劇場で販売されるパンフレット&限定版Blu-ray。パンフレットは72Pとボリューム満点で、これは「あそこがよくわからなかったなー」というままにならないよう、細かい部分まで盛り込まれた内容になっているから。装丁やデザインも凝っているので、ぜひ映画館へ行った人はチェックしてみてください。

「ガラスの花と壊す世界」は1月9日(土)から公開です。YouTubeで「予習動画」も公開されているので、事前に見ておくといろいろなことがすんなりと入ってくるかも。
劇場アニメ「ガラスの花と壊す世界」予習動画 - YouTube

◆スタッフ
原案:Physics Point『D.backup』(「アニメ化大賞」大賞作品)
監督:石浜真史
脚本:志茂文彦
キャラクター原案:カントク
キャラクターデザイン: 瀬川真矢
メインアニメーター:川村敏江
世界コンセプトデザイン:六七質
画面設計:竹内志保
色彩設計:中尾総子(Wish)
美術監督:吉原俊一郎(美峰)
撮影監督:髙橋賢司(旭プロダクション)
音響監督:本山哲
音響制作:ダックスプロダクション
音楽:横山克
音楽制作:ポニーキャニオン
制作:A-1 Pictures
◆キャスト
リモ:花守ゆみり
デュアル:種田梨沙
ドロシー:佐倉綾音
スミレ:茅野愛衣
◆あらすじ
2100年人類滅亡!?
色とりどりの光がきらめき浮遊している無重力の空間――「知識の箱」。
デュアルとドロシーはそこで敵と戦っていた。敵、それは世界を侵食する存在――ウイルス。ウイルスに汚されてしまったデータは消去しなければいけない。
それが彼女たち「アンチウイルスプログラム」の使命だった。
「知識の箱」には、地球上のあらゆる時代やさまざまな場所が記録(バックアップ)されていた。そのデータを収集している存在こそが「マザー」。
「ViOS」というこの世界をつかさどるシステムの中で動いている環境管理プログラムだった。人類の死滅した世界で「マザー」はデータを集め続けていたのだ。
あるときデュアルとドロシーは、ウイルスに襲われているひとりの少女を救う。
「リモ」と名乗る少女は記憶のほとんどを失っていた。
デュアルとドロシーは、リモの正体を探すために、この「知識の箱」をめぐりはじめる。「マザー」の真意とは? ウイルスがなぜ発生するのか? リモの正体とは?
――旅の果てに少女たちは真実を目撃する。
©Project D.backup
・関連記事
「ガラスの花と壊す世界」ワールドプレミア舞台挨拶、「未来の私にとってかけがえのない経験」と初主演の花守ゆみりさん語る - GIGAZINE
ゲーム発売直前にアニメ化が発表された「蒼の彼方のフォーリズム」の原作&アニメメインスタッフ対談 - GIGAZINE
「『攻殻機動隊 新劇場版』が新たな種を生んだ」、プロダクション I.G石川光久社長に話を聞いてきた - GIGAZINE
「攻殻機動隊」という器はいろいろなものを吸収できる、攻殻機動隊 新劇場版の黄瀬和哉総監督&脚本担当・冲方丁さんにインタビュー - GIGAZINE
牙狼プロジェクト最新作劇場版「媚空-ビクウ-」公開を控えた雨宮慶太総監督にインタビュー - GIGAZINE
押井守監督に「TNGパトレイバー 首都決戦」ディレクターズカット公開の経緯についてインタビュー - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in インタビュー, 映画, マンガ, アニメ, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Difficulty of being able to make freely,….












