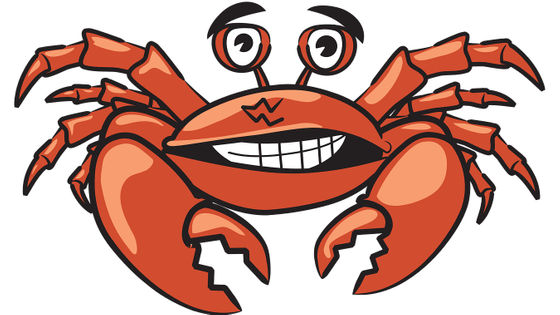人は怠惰だから失業しているわけではない、否定するべき「仕事についての神話」とは?

多くの人々は子どもの頃から「真面目に努力していればよい仕事に就くことができる」「一生懸命働けばよい人生を送ることができる」と教えられており、大人になっても大勢がこれらの価値観を持ち続けています。ところが、こうした「仕事に関する神話」にはさまざまな問題点があるとクイーンズランド大学で教育哲学などを研究しているLuke Zaphir氏が主張しています。
No, people aren’t unemployed because they’re lazy. We should stop teaching children myths about work
https://theconversation.com/no-people-arent-unemployed-because-theyre-lazy-we-should-stop-teaching-children-myths-about-work-153643
世間は「勤勉に生きることが良い結果をもたらす」という信念を好んでおり、良い学校へ行って良い仕事に就き、一生懸命働くことで良い人生を送ることができると広く言われています。大人もこうした考えを子どもに伝えていますが、Zaphir氏は「真面目に生きれば良い仕事に就くことができる」とする信念には問題があると指摘しています。
1つ目の問題としてZaphir氏が挙げるのが、この信念が持つ「成功する人はそれに値する努力をしてきた」という含意です。この考えは、「給料が高い仕事に就けない人はそれに見合う努力をしてこなかった」という意味へと容易に裏返ります。2つ目の問題として挙げられているのが、「人間は単に仕事をするだけでなく、より野心的で評価が高い仕事に就くべき」という考えに陥りがちだという点です。この思考も、人々が良い仕事を得られないのは自分自身のせいであるという自己責任論に帰着しやすいとのこと。

Zaphir氏は、以下の2つの「仕事に関する神話」を否定し、子どもに教えるのをやめるべきだと主張しています。
◆神話1:個人的な成功は努力から生まれる
実力主義に基づくこの神話は、市場経済に対する個人の自由や市場原理を重視する新自由主義の言説で共通して見られるものです。「誰もが努力をすれば成功をつかむことができる」というこの主張は理想的なものですが、これにはダークサイドがあるとZaphir氏は指摘しています。
Zaphir氏が指摘するダークサイドとは、この言説を信じる人は「誰かが成功していないのはその人の努力が足らなかったからだ」と信じやすいという点です。多くの人が成功していない人をまとめて「怠惰であり、愚かであり、主体性がない」と断じていますが、これはモーダストレンスの間違いだとのこと。
モーダストレンスとは「間接証明」や「対偶による証明」を指す言葉であり、ラテン語で「否定によって肯定する様式」という意味を持ちます。正しいモーダストレンスとは、「1:PならばQである」「2:Qは偽である」「3:従って、Pは偽である」という手順を踏みます。ところが、モーダストレンスを誤解する人々は「1:AはBを引き起こす」「2:Bが起きなかった」「3:従って、Aは起きなかった」という間違った手順で物事を考えてしまうことがあります。
Zaphir氏は、個人的な成功が努力に依存すると考える人々が「1:努力は成功を引き起こす」「2:成功が得られなかった」「3:従って、努力が行われなかった」という風に考えがちだと指摘。実際には、必ずしも努力したからといって成功するとは限らないにもかかわらず、このように間違った論理で「成功しなかった人は努力していない」と非難しがちだそうです。
多くの政治家やリーダーはモーダストレンスの間違いに基づいて、「多くの若者が就職できないのは怠惰や努力不足だ」と信じています。しかし、現実には倒産やパンデミックで仕事を失ったり、体系的な人種および性差別や自然災害、不十分な経済政策によって失業したりすることが十分に起こり得ます。また、成功の大きな因子として「裕福な家庭に産まれる」ことが重要だとの研究結果もあり、必ずしも努力したからといって成功が得られるとは限らない現実があります。

◆神話2:野心的で社会的評価が高い仕事に就けないのは恥である
多くの人々は「特定の仕事は他の仕事よりも権威があり、その仕事に就いている人は多くの努力をしている」と考えており、しばしば「その職業の人が稼ぐお金」が評価の指標となります。この社会的な態度は、「高い賃金を得る仕事は社会的な価値が高い」というバイアスを生み出し、企業のトップが高い給与を得ることに納得感を与えるものです。
その一方で、このバイアスは「給与が低い仕事に就いている人々」への過小評価を生み出しているとZaphir氏は主張しています。たとえば、看護師は最前線の医療スタッフとして社会で重要な役割を果たしていますが、同じ現場で働く医師と比べると給与はかなり低く抑えられています。また、子どもたちを教育する教師も、パンデミックで遠隔授業に移行する中で大量の仕事をこなしていますが、社会的に見てそれほど高い給与をもらっているとは言えません。
さらに問題なのが小売業や清掃業者、配送業者といった仕事に就く人々へのバイアスです。これらの仕事は熟練した専門知識が必要ないケースもあるため低く見られがちですが、社会を回すために必要不可欠な存在であり、他人に奉仕するという点ではパイロットや医師、弁護士のような高収入な職業と同じ立場だとZaphir氏は指摘。一方、「仕事に就くための訓練にかかる時間が重要だ」とする意見に対しては、仕事に就くのが大変なアーティストやクリエイティブ職の人々はそれほど高収入ではないと反論しています。
Zaphir氏は、社会的な評価が高い仕事に就くことが人生の満足につながるのではなく、雇用保障や仕事への自律性、ワークライフバランスこそが仕事の満足度に重要だと主張。子どもたちに仕事について話す場合は賃金に焦点を当てるのではなく、仕事が持つ意味や自律性、ワークライフバランスについて話すべきだと述べました。

・関連記事
若者が職に就けない問題は世界中で発生しており10年以内に6億もの仕事が新たに必要 - GIGAZINE
パンデミックでは失業だけでなく「努力と報酬の不均衡」が問題になっているとの指摘 - GIGAZINE
アメリカの失業率は「過小に算出」されている、真の失業率は「26%超」という主張 - GIGAZINE
失業率2.3%と歴史的低水準を記録しても必ずしも喜べない理由 - GIGAZINE
「子どもが成功するのに必要な要素」が800人の子どもを30年に渡って追跡した結果判明 - GIGAZINE
遺伝子研究で「才能ありで生まれるよりも金持ちに生まれる方がいい結果を生む」という結果が発表される - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article People are not unemployed because they a….