「日中の太陽光不足は夜間の電灯よりも悪い」とノーベル賞受賞の時間生物学者が解説

アメリカの時間生物学者でノーベル生理学・医学賞の受賞者でもあるマイケル・ロスバッシュ氏が「日中の太陽光不足は夜間の電灯よりも悪い」と発言しています。
Chronobiologist and Nobel Laureate in Medicine Michael Rosbash: ‘Lack of sunlight during the day is worse than electric lighting at night’ | Health | EL PAÍS English
https://english.elpais.com/health/2023-12-01/chronobiologist-and-nobel-laureate-in-medicine-michael-rosbash-lack-of-sunlight-during-the-day-is-worse-than-electric-lighting-at-night.html
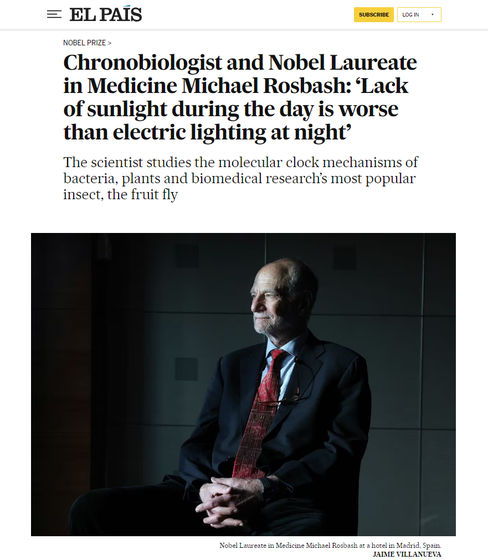
ロスバッシュ氏は2017年に「概日リズム(体内時計)を制御する分子メカニズムの発見」の業績で、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。概日リズムは約24時間周期で変動する生理現象で、食欲・睡眠欲・性欲などを調整したり、喘息発作のタイミングを調整したりするのに関わっています。
概日リズムは動物・植物・菌類・藻類などほとんどの生物に存在しており、ロスバッシュ氏はノーベル賞の受賞スピーチでは「遺伝子の50%が概日リズムによって調整されている」と発言していました。しかし、2023年11月に行われた講演では「遺伝子の少なくとも70%が概日リズムによって調整されている」と発言しています。
この数字の違いについてロスバッシュ氏は、「過去6年間で行われた最新調査の結果により、この数字は更新されました。50%という数字はげっ歯類の研究から得られた数字ですが、2019年にはついに霊長類のヒヒを対象とした大規模な研究が行われ、概日リズムによって調整されている遺伝子の割合が70%であることが明らかになりました」と語っています。

ロスバッシュ氏は時間生物学の起こりについて、「ほぼ50年前、私と同じ大学で教授を務めていた友人のジェフリー・C・ホールを通じて時間生物学は始まりました。彼はその時すでにハエの神経遺伝学に取り組んでおり、概日リズムについても理解していました。そして、私は彼の研究に役立つ可能性のある研究の専門知識を持っていました」と語りました。
ロスバッシュ氏はキイロショウジョウバエを使用して概日リズムに関する研究を行いました。ただし、ハエは10万個のニューロンしか持っていないのに対して、人間は860億個ものニューロンを持っています。そんなハエと人間の概日リズムを結びつける理由について、ロスバッシュ氏は「哺乳類の方がニューロンの数が多くなりますが、ニューロンで起こっていることは基本的に同じです。そこから、我々はニューロンを脳科学と行動に関するより一般的な質問の窓口として利用するようになりました」と説明しています。
また、「24時間15分」という周期を持つ概日リズムの役割について、ロスバッシュ氏は「人間の場合はわかりませんが、他の動物からの情報はあります。羊やげっ歯類のように、繁殖の点で季節性を持つ動物がいます。彼らの生理機能は季節により変化し、日の長さも季節によって異なります。生殖生理を制御するために、これらの動物は概日リズムのオフセットを1年を通して変化する日照周期の長さ、つまりは日光の量と比較します。あくまで推測ですが、羊やげっ歯類は概日リズムを季節の変化を測定するためのツールとして利用するのではないでしょうか」と語りました。

ハエと人間の共通点のひとつが睡眠および昼寝です。睡眠および昼寝の生物学的目的について問われたロスバッシュ氏は、「詳細はわかりません。ですが、記憶は睡眠中に強化され、神経細胞の形態は睡眠中に変更されることが明らかになっています。ただし、これが睡眠の主な目的ではないと思いますし、ハエと人間の睡眠にどのような共通点があるのかもわかっていません。私の推測では、細胞内の重要なエネルギー源であるアデノシン三リン酸(ATP)の再充電などの代謝に関係しているのではないかと思います。脳はATPの最大の消費者で、恐らく代謝による充電の必要があるのでしょう」と自身の見解を述べました。
現代では至るところにディスプレイが存在しており、就寝前にスマートフォンの画面を眺め続けているという人も少なくないはずです。こういった習慣が人間におよぼす悪影響について、ロスバッシュ氏は「夜間に電光に照らされることは問題ですが、その深刻さを見積もることは困難です」と言及。最新の研究によると、日中の太陽光不足は夜間に電灯にさらされることよりも悪いことであることが明らかになっているそうです。また、睡眠問題の多くはこれらの環境要因に対処することで改善することができる模様。
また、自然の中で数週間にわたりキャンプを行う人々を対象とした研究では、電灯にさらされる機会が減った被験者の睡眠の質が高まり、暗くなったら寝て、朝になったら起きるという習慣に改善されたことが明らかになっています。他にも、ブラジルで行われたジャングルで暮らす人と都市部に移住した人の睡眠習慣を比較した研究でも、都市部に移住して電灯にさらされるようになった人々の睡眠の質が悪化し、入眠タイミングが遅くなることが確認されているそうです。これらの研究結果を例に挙げながら、ロスバッシュ氏は「現代の人々は少し睡眠不足のようです。16時にセミナールームの照明を消すと、すぐに聴衆の半分がいびきをかきはじめます。十分に休息をとった人の場合、このようなことは起こりません。完全に睡眠不足の文化です」と述べ、明るい電灯に照らされながら日々を過ごす現代人が明らかに睡眠不足に陥っていると指摘しています。
交代勤務や夜間勤務に従事する労働者は、がんを発症する可能性があることが国際がん研究機関(IARC)の研究により明らかになっています。こういった仕事に就く人々に対して、ロスバッシュ氏は「コツは夜が昼であるかのように振る舞うこと、あるいはその逆であることです。これを厳密に行えば、体は何が昼で何が夜なのかを認識していないため、ほとんどの問題を回避できます。重要なのは、どのくらいの光が入るか、そしていつ食事をするのかです。光が入らない部屋で8時間の睡眠をとり、睡眠が中断されないようにし、その間は食事を取らないようにすれば、体が違いに気付くことはありません。問題は家族や世間との交流くらいでしょう」とアドバイスを送りました。

また、夜の間食が肥満やメタボリックシンドロームのリスクを高める理由について、「仮説としては概日リズムによって調整されるDNA損傷修復システムに関連しているというものがあります。植物はセロリに豊富に含まれるソラレンなど、食べられることを避けるために毒素を生成することがあります。夜の間食は、人間がその時間に除去する準備ができていない毒素を取り込むようなもので、アメリカで結腸がんなどの上皮がんが大流行しているのは、夜の間食のせいではないかという説もあります」とロスバッシュ氏は語っています。
・関連記事
約4秒の昼寝を1日1万回することでヒゲペンギンは11時間以上の睡眠時間を稼ぐ - GIGAZINE
「チーズを食べると悪夢を見る」「人間は5時間睡眠で十分」など睡眠に関する8つの神話とは? - GIGAZINE
「寝室の換気」で睡眠の質が向上することが4週間にわたる実験で判明 - GIGAZINE
「よく眠れた」と思うことが実際の睡眠の質よりも幸福度に大きな影響を与えるとの研究結果 - GIGAZINE
人間は冬になると夏よりも必要な睡眠時間が長くなるかもしれないという研究結果 - GIGAZINE
理想的な睡眠をしていると寿命が延びる可能性がある - GIGAZINE
睡眠のメカニズムは脳の進化に先立つ可能性、生物は睡眠状態がデフォルトかもしれない - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in サイエンス, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article ``Lack of sunlight during the day is wor….












