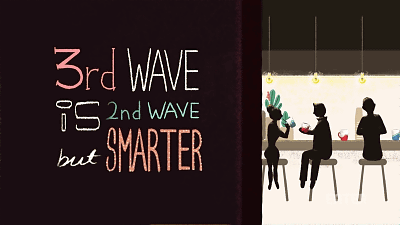隆盛を極めたアメリカのショッピングモールの現在、これからの成長戦略とは?

By Thomas Quine
多くのお店が一か所に集まってさまざまな買い物ができるショッピングモールは日本でも数を増やし、いまやちょっとしたテーマパークにも引けをとらない規模の店舗も見受けられるほど。その起源はアメリカにあるショッピングモールですが、アメリカ国内でも新旧のモールが入り乱れ、世代交代や進化に次ぐ進化を続けています。
Are Malls Over? : The New Yorker
http://www.newyorker.com/online/blogs/currency/2014/03/are-malls-over.html
アメリカにおけるショッピングモールの歴史は、1920年頃に始まったと言われています。車が人びとの生活に浸透してきたこと、そして都市部から郊外へと生活の拠点が移動したことを背景に、広大な土地に大規模な建物を建設し、多くの小売店を集約することで一度に買い物することができるショッピングモールは大きく発展を遂げることになります。
特に1950年代後半から60年代にかけ、アメリカでは郊外型ショッピングモールが著しい発展を遂げる時期に入ります。郊外型大規模ショッピングモールの産みの親として知られているのは、オーストリア・ウィーン出身の建築家であるビクター・グルーエン氏で、多くの施設のプランニングを担当したグルーエン氏は1956年、ミネアポリス州に建設されたサウスデール・ショッピングセンターを手がけ、成功を収めました。

By James Vaughan
しかし50年以上を経た現在、多くのショッピングモールでは老朽化が進んでいます。1969年にオハイオ州トレド郊外に誕生し、百貨店のSears(シアーズ)やデパートのJ. C. Penney(J.C.ペニー)、映画館などの施設を併設して多くの買い物客を集めていたウッドビル・モールも、すでにその役目を終えてしまっています。
アメリカでは、このように本来の役目を終えて廃虚となりつつあるモールが多く存在しており、それらを集めたサイト「DeadMalls.com」が開設されているほど。役目を終えた後も地域のコミュニティカレッジとして再生するもの、企業が購入して社屋に使用されるもの、また教会として生まれ変わるケースもありますが、多くの建物には老朽化が見られることもあり、最終的には取り壊されることがほとんどです。

By Nicholas Eckhart
この状況を、アメリカでも最大の不動産デベロッパであるCaruso Affiliated社のCEOであるリック・カルーソ氏は「今後10年から15年の間に、典型的なアメリカ型のショッピングモールは過去の遺物となっていくでしょう。もはや、住民・小売業者・コミュニティからのニーズに合致しない存在となっていくと考えられます」と、全米小売業協会の年次総会の場で発言しています。
その要因の一つは、オンラインショッピングの成長であると言うことができます。2013年第4四半期におけるアメリカでの小売業の売上のうち、オンラインショッピングが占める割合は6%に達しており、2006年の基準と比較してほぼ2倍の成長を見せる状況になっています。この状況を受け、かつてはどのモールにも店舗を構えていたアパレルチェーンのGAPも、すでにショッピングモールを成長の基軸から外しており、今後はアジアを中心とした地域への進出を主な成長戦略として掲げるに至っています。

By Conny Sandland
もうショッピングモールが生き残る方法はないのでしょうか?カルーソ氏は生き残りのための方策として、「施設のリノベーション」を挙げています。近年のモールの多くは、外光が施設内に差し込むような開放的な空間を提供するものが多くなっており、灰色のコンクリートで囲まれた「グレーボックス」と呼ばれる旧来の施設は明らかに現代の主流から遅れていると言うものです。
建物内に人びとが行き交う「ストリート」を作り、ヨガ教室や各種イベントを行える「広場」に人びとを集め、単なる「買い物の場」から「人びとが集う場」に変えて行くことで集客力を向上させようとするのがその狙いですが、実際には想定よりもうまく実現が進まないことも。施設全体の売上が急激に低下しているため、改修に費やせる予算を確保できないという事態が起こっています。
モールの中にはすでに施す手立ても見いだせず、消えゆくのを待つしかないケースも多数存在します。そんな中、新たな活路とされているのが、海外進出という戦略です。すでにアジアの各地域にはアメリカ系の小売店が多く進出しており、中国と韓国をターゲットにした現地法人を設立したモール運営企業のタウブマン・センターのようなケースが見られるようになりました。海外での事業展開を広げるため、日本のイオンもつい先日ベトナムに進出し、アジアの国々に店舗を立ち上げ始めています。

By brian wallace
前出のカルーソ氏が担当したモールのうち、ザ・グローブとアメリカーナ・アット・ブランドの2つは、面積あたりの売上額が全米トップ15にランクインするモールとして成功を収めています。敷地内には数百戸の高級マンションを構えるアメリカーナ・アット・ブランドは1つの小さな街と呼べるほどの規模を持ち、集客・出店の両面で盛況を呈しています。
このように、従来からの「グレーボックス」タイプのショッピングモールには厳しい時代が訪れていますが、対応次第によっては明暗がはっきり分かれる状況が生まれており、人びとの青春時代を彩ったショッピングモールにノスタルジーを感じることも少なくありません。フォトグラファーのマイケル・ギャリンスキー氏もそんな懐かしい時代を送った一人で、当時の様子を収めた写真集「Malls Across America」を出版しました。そしてこの写真集はいま、ネットショップの代表格であるAmazonで販売されています。

一時期は人気を集めた店舗業態であっても、市場や消費者の嗜好の変化によって路線変更や撤退を余儀なくされることはよくあること。いつの時代でも柔軟な対応をとり続けることが、市場で生き残り続けるために何よりも大切であるということは間違いなさそうです。
・関連記事
ウォルマート・カルフール・テスコなど世界的な総合小売業はどの国へ進出しているのか - GIGAZINE
世界最大のスーパー「ウォルマート」VS世界最大の通販サイト「Amazon.com」 - GIGAZINE
有料会員制でありながら売り上げを伸ばし続けるコストコ成功の秘密とは? - GIGAZINE
なぜ廃墟になったのか、ギリシャのあまりにも美しい海を望む酒場 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by darkhorse_log
You can read the machine translated English article What is the current growth strategy of t….