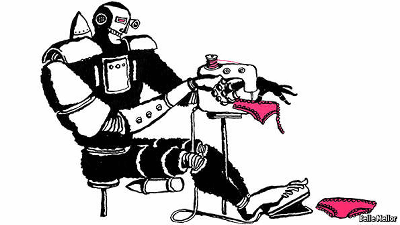中国の低賃金な労働力が終わりを迎え、2050年に向けて世界はどうなっていくのか?

by Carlos Adampol Galindo
2015年11月、中国はついに一人っ子政策を廃止しました。安価な労働力のおかげで世界最大の輸出国となった中国でしたが、さまざまな理由から今後は緩やかに労働力を低下させていくものと見られています。これから2050年にかけて、中国や世界の製造の形がどうなっていくのか、アメリカを拠点とするアパレルメーカーのリーバイスを例にウォール・ストリート・ジャーナルが見解を示しています。
As China’s Workforce Dwindles, the World Scrambles for Alternatives - WSJ
http://www.wsj.com/articles/as-chinas-workforce-dwindles-the-world-scrambles-for-alternatives-1448293942
1853年に創業されたリーバイスは1960年まで、アメリカのみでジーンズの製造を行っていました。しかし製造コストを下げるため、1966年に香港での製造を開始したことを皮切りに、メキシコやヨーロッパ、アジアにも進出。そして1986年ごろからは工場を中国に移しだします。
中国は労働力の多さを利用して1980年から2007年までで海外への製品出荷を6700%も上昇させ、アメリカを差し置いて世界最大の輸出国となりました。アメリカやヨーロッパの工場では機械を使って作業を自動化することでコストを下げる戦略を行いましたが、当時の中国の労働力のすさまじさは「機械には勝てない」ものだったと、リーバイスのヴァイスプレジデントであるデイビット・ラブ氏は語っています。2002年後半の中国における労務費は1時間あたり60セント(約74円)だったそうです。

by Ken Driese
しかし、これまで中国の工場で製造を行いコストを下げていたリーバイスですが、近年はサプライチェーンの見直しが行われています。中国の生産年齢人口増加はピークを迎えており、いわゆる人口ボーナスは終わりが見え始めています。2012年時点の中国の生産年齢人口は約9億3000万人ですが、2050年までに2億1200万人ほどの生産年齢人口が減少するだろう、というのが国連の見解です。2億1200万人という数字は、大体ブラジルの総人口と同じぐらいです。
中国における15歳から59歳までの生産年齢人口の変動は以下の通り。左の青い部分が2011年頃までの実際の数値で水色の部分が国連による予測です。中国の生産年齢人口は2012年に初めて減少の傾向を見せており、今後その傾向は加速するものと考えられています。

また、現在の生産年齢人口が高齢化し、2050年における60歳以上の人口は2015年の2倍ほどになると考えられており、親の面倒を見るために都市から田舎へと移り住む人口が増加して、都市部の労働力が減少する可能性もあります。
さらに、安価だった賃金が急激に上昇しているのも、これまでのような労働力を生み出せなくなる原因の1つ。かつては1時間あたりの労務費が約74円だった中国ですが、今では沿岸部の労務費は1時間あたり15.6ドル(約1900円)となっており、アメリカの22.68ドル(約2800円)と比較しても大きな差はありません。景気が緩やかに低迷するにつれて勢いは緩やかになっていくものと見られていますが、それでも今後数十年にかけて賃金の上昇は避けられません。
以下のグラフ下部にある赤い線が中国における賃金の上昇を示しています。

中国の南沙区で働く28歳の青年は基板の組み立てなどで生計を立てていますが、家を買えるほどの年収を得ています。青年は「今ではさまざまなチャンスがあります。私は得意なことがしたいので、もしバッテリーに関して仕事を行う機会があれば、ぜひ挑戦したいです」と語っています。
中国の労務費が上昇したからといって、リーバイスが値上げを行ったわけではありません。では、どのようにコストを抑えているのかというと、中国の工場における機械の導入がカギ。リーバイスはそれぞれのデニムが別のデザインに見えるように異なるパターンのエッチングを行えるレーザーを導入し、「お針子がポケットの模様を縫っていく作業」「1つ1つ手作業で描かれていた複雑なパターンを描く作業」も自動縫製マシンやデジタルプリンターで機械化したとのこと。さらに、サプライヤーの数をこれまでの60%に、購入する生地の量を半分に減らすことでコストを抑えているそうです。

中国における産業ロボットの売り上げは群を抜いており、これからも上昇してくと見られています。

よりコストを下げるため、中国より人件費が安いカンボジアなどで製造を行うこともあるリーバイスは、さらに人件費が安く、若年層の人口が多いアフリカ諸国にも注目しているとのこと。
また、近年は「消費者一人一人の好みに合わせて製造する」という形が主流になりつつあり、中国国内の変化だけでなく、製造・消費の形そのものにも変化が起こっています。リーバイスにおいて「多様な商品をインターネット上で簡単に購入できる」ということは既に実現しており、現在は「消費者が自分の体をスキャンして各パーツの数値をアップロードすることで各人にピッタリな洋服を購入できる」という試みがテスト中です。
これらの変化によって「中国沿岸部の巨大な工場で大量生産された商品を海外に輸出する」という製造の形が変化し、それぞれの地域の好みに合わせた商品を小さな工場で製造する、という形が増えていくと見られています。実際に、中国で製造されヨーロッパでブームを巻き起こしたスキニージーンズは、ポーランドとトルコで予想外にヒットしたため、現在は両国に小さな工場が置かれています。
以下のグラフは、中国の輸出量が2017年にピークを迎え、それ以降は緩やかに輸出量を減らしていくという予想。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、これら製造の変化によって、アメリカの中国に対する貿易赤字は2042年までに黒字に向かうと予測されているとのこと。さらに、15年前、中国の生産年齢人口や賃金の安さに勝てず6000人もの従業員が解雇されたメキシコのリーバイスでは、中国の生産年齢人口減少と賃金の上昇によって再び働き口が増えるのではないかと期待されています。

by Chris
近年は3Dプリンターの技術が向上し、また価格も安価になっていていることから、「2050年までには3Dプリンターが服や食べ物、機器などを作りだすようになり、製造の形が大きく変わる」と考えている技術者も存在します。これらを踏まえ、ウォール・ストリート・ジャーナルは、大量生産・大量消費という形から、より個人に合わせたもの、商品の到着が速いもの、環境に優しいものが選ばれるようになってくるだろう、と見解を示しました。
・関連記事
ファストファッションの裏側にある知られざる世界 - GIGAZINE
たった3分で100年間の男性ファッションの変遷が分かる「100 Years of Men’s Fashion in 3 Minutes」 - GIGAZINE
女性ファッションの100年の歴史を一挙に振り返るとこうなる - GIGAZINE
鬼編集長として恐れられるVOGUEのアナ・ウィンターにあれこれ質問ぶつけてみたよムービー - GIGAZINE
有名人の着ている服を分解してどこのブランドの何かがわかる「Famous Outfits」 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by darkhorse_log
You can read the machine translated English article What is the world going to be going for ….